no">
2015年07月23日
神の集まる島 神津島探訪 まとめ
伊豆諸島の神津島へ行って来ました。東海道線に乗っている時に「神津島ホワイトビーチきっぷ」というお得な切符の広告を見掛け、これは機会であると思い、行って来た次第。
8500円で熱海から出航する高速船の往復券、島内のバス乗り放題、公共の温泉に入り放題、郷土資料館無料という特典があり、通常の運賃は片道で8200円ですのでかなりお得です。


熱海港を10:50に出港。

40分ほどで大島に停泊。

ここで機関に不具合が出たそうで10分ほど遅れたが、11:55に大島を出港。
30分ほどで利島、

鵜渡根島

新島を横目に見つつ、13時に神津島港に入港。


まずは港の観光案内所にてテント場の使用申請と島の情報収集。
それと、山に登る予定なので、その下山後は宿に泊まろうと民宿を手配してもらう。事前に行おうと思ったが、シーズンだからかどこも一杯だったのだ。運良く空いている宿があり、予約して貰う。
島に入って歩き出すと、まずは眼前に聳える天上山の荒々しい姿。

荒々しい天上山の対称的に優美な白浜が延びる前浜海岸。

「水配り神話」のモニュメントが立っています。


伊豆諸島の神々が神津島に集まって、如何に水を配分するかを協議したという
まずは郷土料理が食べたいなと、観光案内所で教えて貰った所へ向かった所、残念ながら本日貸切。30分ほど坂道を歩いたのがフイになったが、「佐久市友好の碑」というのを見掛けた。
それによると、平安時代中期の武将・藤原秀郷の子孫である藤原定国は伊豆諸島を領して神津島に館を構築した。その後、数世代が神津島に留まり、姓を神津氏とした。その後、甲斐国の武将・小笠原長清を守るため信濃の佐久地方に移ったという。
この縁で、神津島村は佐久市と姉妹都市交流があり、伊豆諸島と本州との関わりを示す一例であり、やはり来ないと知らない事はあるなと実感。
高台からの前浜海岸

島の集落を望む

島の中学校の校庭は芝生が美しい

集落の方へ向かう。神津島は港前の集落約4キロ平方メートルの地域に約800世帯、約1900人の人々が生活している。神津島に一軒というスーパーマーケットにて食材を色々と買い込むが、残念ながら地元の食材は少なかった。
ここでややにわか雨が。
再び歩いて個人商店のお店を覗くと、「盛若」という神津島の焼酎や、かなり希少な青ヶ島の焼酎をはじめ、食材も地元の物が多かった。
菓子パンなどは下田の物が多く、菓子パンの中には「きりんちゃん」というどう見ても「のっぽ」に似せたパンがあったので購入。

下田との定期船がこういう所に活きていると感じる。
そう言えば、店の人が聴いていたラジオもSBS静岡放送だった。
少し歩いてみると村内の道路は入り組んでおり、個人経営の商店が多く20〜30メートルごとに商店があり、島人口1900人にしては多いのでは、とも思えるくらい。各々が様々な物を扱っていて、業態分けが出来ない雑多な感じが面白い。

狭い路地の中を原付が走り回るが、案の定、ヘルメットを被ってない人が多い。

食事の第二候補にした中華料理店が開いていなかったので、神津島役場の近くにあったあずまやで、海を見ながら先程買ったパンやお惣菜などを食べ焼酎も少し頂く。

曇りがちで風もあるので涼しいくらい。
おたあジュリア顕彰碑

おたあジュリアは、秀吉の朝鮮の役の際に連れてこられた朝鮮人女性。
キリシタン大名の小西行長に身柄を引き渡され、後にキリスト教に改宗し「ジュリア」は洗礼名、「おたあ」は日本名を示す。
関ヶ原の戦いにて敗れた行長が処刑され小西家が没落すると、おたあの才気を見初めた徳川家康によって駿府城の大奥に召し上げられ、家康付きの侍女として側近く仕え寵愛を受けた。
しかし、慶長17年(1612年)の禁教令により駿府より追放され、神津島へと相次いで流罪となった。
食べ終わって再び歩き、島の鎮守である物忌奈命(ものいみなのみこと)神社にお参り。三日間、島に滞在するご挨拶。
この神社は出雲神話の大国主命の御子・事代主命が出雲の国譲りの後、出雲を出て伊豆諸島にやって来て島々を拓き、神津島の女神・阿波咩命(あわのめのみこと)との御子として生まれたのが物忌奈命である。

社殿は江戸中期の造りで唐破風が重厚な造り。

境内も掃き清められていて、式内社の風格があります。

しめ縄の張ってある木の洞

時折見かける奉納された神社内の砲弾


観光客が多い島だからでしょうか



神社の境内から延びる石段を降りると、そこは来た港の目の前。

バス停にてバスに乗り込み、バスは三分ほどでキャンプ場へ。

キャンプ場は静かな入り江である沢尻海岸にあり、トイレ、シャワー、炊事棟があり、万全の備え。ここが無料で使用できるとは。幕営していたのは5組ほどである。


観光案内所で前日は風が強かった事を聞いていたので、壁がある側にテントを張る。30分ほどで設営し、温泉へ向かう。

神津島温泉保養センターはバスで行けるがバスはもう運行が終了してしまった時間なので、10分ほど歩いて行く。この施設も元は大人800円であるが、ホワイトビーチきっぷで入り放題である。
内風呂と露天風呂があり、水着着用の露天風呂は大・小・展望風呂があり、自然の岩場を利用した大露天風呂は、100人は入れるという大きさで、海に面しており開放感は抜群。ただ、真っ暗なので景色は見えず眼鏡を外すと足元も見え辛いので、岩場を歩くのも危ない。故障しているらしく湯温がぬるく水着着用の為、余り気持ち良いとは言えない。明るい時に来たいかなと。
テント場に戻り、夜の海と他のキャンプ客がやってる花火を見つつ、スーパーで買ったお惣菜を食べ焼酎を飲んでいたらそのまま寝てしまう。初日終了である。
二日目。天気は良く、本当は天上山に登ろうとしたが、天気予報では昼から雨が降るというので、予定を変更して島内散策をする事に。
昨日、島内に在るパン屋さんで買ったパンを食べて、朝食を済ませた後、島の北側に向かって散策。


海岸には所々に天草を干している。

伊勢エビやとこぶしも豊富だそうだ。そう言えば、密漁を警告する看板も多い。

先日の温泉保養センター。

露天風呂が道路から見えるんですが。(水着着用だけど)

その先は覆い被さるかのような断崖のすぐ脇にある道路を歩く。


ここは大きな地震が今来たら海側にも山側にも逃げ場が無く怖いな・・・と思わせる。
港の周辺やテント場の辺りとは違って、この辺りは海岸も変化に富んだ流紋岩という岩の岩礁と松が連なり、見ていて飽きない。



一番先まで歩いて行く

流紋岩の中でも金雲母流紋岩という岩が日光を反射して輝くメッポー山という所。

岩山が亀の様な形をしている事から、亀山とも呼ばれたそうだが、実際に亀の産卵もあるという。

歩き始めて一時間ほど。ここには長浜キャンプ場があるが、誰もキャンプしている人は居ない。

静かなキャンプと海水浴に徹するなら良いが、市街地から離れているので、ある程度、食料などを準備しないとここでは大変だろう。
そしてここには阿波命神社がある。(が、始め気付かず通り過ぎてから気付く)


この神社は前日の物忌奈命神社に次ぐ式内社であるが、集落の側に在る物忌奈命神社に比べると、やや寂しい印象である。ただ、神社の社殿の様子などが、続日本後紀という文献の記述と一致している、古代神社の立地を今に伝える貴重な神社であるという。
阿波命は事代主の来島を祈り、この地で宴を開いて歓迎し、事代主が島を離れる時は、この地で水平線で見えなくなるまで別れを惜しんだという。
その事から、この長浜海岸には白砂と赤や黄色など色とりどりの玉石があり、別名「五色浜」とも言われるが、石を持ち去ると祟りがあるという。

定期船が

更に一時間ほど歩くと、海岸に人工の構造物が。近寄ってみると、レールが敷かれていた跡があった。

近くに案内板があるので、それを見ると、かつて採掘されていた抗火石という石材の運び出しを行っていた跡との事。

抗火石は新島の印象が強かったが、かつては神津島でも採掘されていたという。

抗火石は流紋岩の一種で、スポンジ状の構造から鋸や斧で容易に切断でき、その軽量性、耐火性、断熱性、耐酸性から多くの用途に使用されている。

その特性を利用し、過去には抗火石で作られた石の船も存在した。伊豆諸島以外ではイタリアのリーパリ島のみが採掘地である。
山側に崩落が著しい山があり神戸山というが、この山全体が抗火石であるという。

昭和17年に日産化学工業が採掘の為に施設を設けた。当時は道路が通じていなかったので、神戸山に支柱を設けて海まで索道を張り、山で採掘した石材をこの索道で運び、海側でトロッコに乗せ、運搬船に荷積みした。この湾には採石場で働く人々が多く住んでいた。
需要の減少により昭和30年にこの施設を用いた荷積みは行われなくなったが、島内で用いる住宅や道路の石垣などの石材として平成12年まで採石が行われていた。
坑火石の切り出し場から15分ほどで赤崎海水浴場。

ここは岩礁を渡れるように木道が整備されているのと、それを利用した海水浴場である。

この時も風が強く波もあったが、岩場に囲まれているので海水浴場は静かで珊瑚や小魚の大群が入ってきたりと魚影豊か。それを見る為かダイビングの人も多い。でもシュノーケリングでも見られそう。

岩場に遊歩道と共に櫓が組んであって、様々な高さから海に飛び込めるようになっている。



肌寒いので海水浴をしているのは10人程度だったが、海遊びには興味が無い私も、ここはもう少し暑い時期に来て海水浴をしたいと思わせる所です。

遊歩道を歩いていくと展望台があり、式根島、新島、利島と来た時に船から見た島々を眺めることが出来る。



ただ、海側で傷みもあるからか、通れない箇所もあり、行先に渡れない所もあった。

後で知ったが、昨年の伊豆大島での土砂災害の時の大雨では神津島も豪雨により所々で遊歩道が崩落してしまったという。

遊歩道が通じていなかったので車道のトンネルを抜けたが、その先のトンネルが行き止まりであった。

これも後で知ったが、平成12年の三宅島の噴火の際、神津島・新島・利島では震度五クラスの地震が頻発し、神津島では死者一名を出している。
その地震により、先の道路が神戸山の崩落に巻き込まれてしまった時から工事が止まっているとの事である。港の近くにあった公園には地震の碑があったのを思い出した。風光明媚ではあるが、昔から地震にも見舞われて来た島なのである。
その脇にあった湧き水

赤崎遊歩道のバス停からバスに乗り込み港の方へ戻る。二時間近くかけて歩いて来た道も戻るのは20分ほどである。
港のバス停で降りて、昨日閉まっていた中華料理の店で食事。
この週にあるトライアスロン?な競技会に参加する人が大勢居り、たくさん食べる人たちであった。
歩いている途中で見掛けたスナック・アニメイト



食事の後、このまま島の反対側である多幸湾へ向かおうと思ったが、バスの時間まで時間があるので高台にある図書館に向かう。
図書館がある高台からの眺め

島の図書館は新しいが、余り利用されていないのも感じた。確かに平日であるが、ご年配の人なども居ないのである。高台なので歩いて来るにはやや厳しいというのもあるのかもしれない。使われていないのがもったいないと感じた。
図書館からバス停へ向かう途中、与種神社という神社というより祠があった。

説明版には甘藷先生と呼ばれた青木昆陽を祀った神社で、サツマイモの普及により、島内でも飢餓の恐怖から救われた事でこの祠が建て祀られたという。全国的にサツマイモの普及を讃える神社はあるが、この地でも見つける事が出来、非常に嬉しかった。
バス停から多幸湾へ向かうバスに乗り込む。図書館に居た時は良い天気であったが、ここに来て急に曇りとなり、雨もポツポツ落ちて来た。
こちらのバス路線の運転手さんは話し好きなのか、他の乗客の人と盛んに話をしていた。更に、景観が良い所などでは減速して見所を案内するなど、サービス旺盛である。

神津島空港

バスは神津島空港を経由するのだが、その途中にあった三浦湾の景色が素晴らしく減速してくれたものの、停車では無いので写真を撮れなかったのが残念。

こちらも20分ほどで多幸湾へ到着。多幸湾は神津島港の反対側であるので、強風や波浪によって神津島港に船が停泊できない場合は、こちらが発着になる事がある。
港と言っても周囲には商店・民家らしき物は何も無く、自販機だけがポツンとあるだけ。港の待合所になる建物があるが、利用されていないので閉まっている。
多幸湾の待合所の脇にはカジキマグロに乗った人の像が立っている。

これは神津島村の村の魚がカジキマグロであるからで、伊豆諸島の中でも漁業が盛んな島であり、中でもカジキマグロ漁が盛んである事からであろう。
曇りで雨粒が落ちている事もあって人気は殆ど無いが、白く長く伸びる素晴らしい砂浜と、天上山の山頂近くから海にまで崩落している崩れ地形は迫力抜群である。




その先には砂糠崎という黒曜石が露出している岬がある。


そして、海岸のすぐ側には都内でも有数の湧水が湧出しているなど、神津島の特徴が全てこの地に集まってると言えよう。
港方面に戻るバスまで時間が有るので、周辺を散策。散策路として港の方に抜ける山道もあるが、いつ雨が降りだすかわからないので、周辺を歩くにとどめる。





特に見るべきものなどは無いが、多幸湾キャンプ場があるので覗いてみると、コチラは有料であるものの、管理者が常駐しており冷蔵庫や荷物や貴重品の預かり、炊事場のみならずお風呂付など至れり尽くせりのキャンプ場である。
バスが発車する時間になったのでバスに乗り込み、再びスーパー近くのバス停で降りる。
先日は入らなかった百円ショップに入ったら色々とキャンプ用品もあった。その時、炊事場に炭が捨てられていた事を思い出し、
「これでバーベキュー出来るんじゃね?」
と思い立ち、百円ショップで網や調味料を、スーパーで食材を購入。
他の商店でも食料品を購入していたらバスの時間が過ぎてしまい、歩いてキャンプ場まで戻る事に。
途中の岩穴にて雨宿り


しかも折悪く雨が強く降り始め、靴はずぶ濡れ、中まで水が浸み込み精神的にヘコみながらもテントへ戻る。
すると、近くの旅館に泊まっている団体さんが炊事場を使っているので、先に温泉保養センターに行く事にする。風呂から上がると雨はかなり強くなり傘を差しても濡れるほどに見える。しかし閉館時間が近付きつつあり、腹の減り具合もかなりであるので、雨の中をテント場へ戻る。
もう団体さんは居ないものの、今度は風が強くなり、屋根がある炊事場も雨が吹き込んでくる。そんな事もあって中々火が点かず、食材に火が通るまでかなりの時間を要してしまい疲れた・・・。
朝起きると、昨夜の雨でテントの床面に水が浸み込み、寝袋も濡れてしまってやや気分が落ち込み。
しかし、空を見上げると雲が多いものの青空ものぞかせ、登山の気分は高まった。
コンロに火を点けて水を沸かし、レトルトの粥を温めて熱いお茶を淹れた。朝食も体温を上げようと、温かい物を食べて気分を高める。
登山の準備をし、朝一番のバスに乗り込んで港へ。神津島の天上山は標高574メートルであるが、実質、海抜0mからの登山と言える。島に降り立った時も感じたが、正しく壁のように見える。本当にこの山を登れるのだろうかという不安感もよぎる。
島の中心部である地区を抜けて住宅地となり、天上山方面には「黒島口」と「白島口」という2つの登山口の分岐点がある。今回は最短距離の「黒島口」を選ぶ。
更に標高が高くなっていくと、次第に緑が濃くなっていく。


港から歩き始めて一時間、ここで車道は途切れ登山口となる。
登山口近くに在った風穴


火山らしい
その先に進んでいくと、眼下に昨日見た多幸湾や高処山、秩父山が見える。


改めて地図を見ると、どうやら行き過ぎてしまったようだ。昨日、雨で無かったら多幸湾から港方面へと歩こうと思っていた道だったらしい。戻りつつ、注意深く山側を観察して歩くと、登山道発見。木々で良く見えなかったので見過ごしていた様だ。


この黒島口登山道は神津島の中心集落を見下ろしつつ登れる道である。

序盤はシダが生い茂り歩きづらい。そう感じても、第一歩を踏み出さなければ登山は出来ない。無心になって足を進める。

登山道には「〇合目」との表記が定期的に示されて設置されており、それを目安にして休憩を入れる。次第に歩きやすい道になり、高みを増すたびに海が広く見えてくる。結構な急登だが景色が綺麗なので疲れを感じない。どこで立ち止まっても素晴らしい展望だ。
登山道を30分ほど歩き始めると、学生らしき若者たち15人ほどが追い付きそうだったので先に行かせた。彼らの軽装が気になる。
この頃までは天気は良く青空も見えていたのだが、次第に雲も見え始め、山頂が見えなくなった。

標高が上がってくると雲の中になり、下界の様子も見えなくなった。

学生たちの声は聞こえていたが、姿も見えなくなった。山の様子も木々の緑は少なくなり、灰色の岩の方が多い色彩になる。

この8合目付近に在ったのが、「鬼たちの力比べ」という伝説を示した案内板。力自慢の鬼達が天から降りて来て、ここで50メートルある石を投げて力くらべをしたという、伝説が残っている。
それまで、前述の学生たち以外に人を見ていなかったが、降りて来た人が居た。降りて来た人が「まだ上に行くの?」と聞いて来た。十合目から先がとんでもない強風なのだという。
ここまではまだ風は然程では無かったが、上がる度に風を感じ、15分ほど歩くと十合目の標柱が見えてきた。
十合目の標柱を過ぎたとはいえ 台形型の天上山の門に立ったに過ぎず、ここがゴールではない。むしろ天上山の魅力はこれからである。
十合目の標柱を超えると風がとんでもない強さになり、体感では20m以上はあるのではなかろうか。撤退もやや思い浮かんだが、雨は降っていないのと、この先はやや窪みであるので、風も幾分弱まるかと思い先に進む事にする。
まずやって来たのは、オロシャの石塁と呼ばれる文政の石積跡。
江戸末期、外国船籍の船が日本各地に出没するようになったため、幕府は伊豆諸島の島民に鉄砲と槍を備えさせ、更に外国人が島に上陸した時、天上山に引き寄せて戦えるように石積の防塁を約300mにわたって築いたもの。と説明がある。ただ、実際は石材を切り出していた頃の名残だという。
しかし、ここは先程居た所よりも風が強く崖の側なので、写真を一枚撮っただけで早々と引き返す。晴れていればかなりの展望であっただろうなぁ。
次に千代池(せんだいいけ)へ向かう。天上山の頂上台地には、火口跡に雨水が溜まって出来た幾つかの池があり、中でも千代池は一番大きい池である。
池であるからやや窪みであろうと思い、風も弱まるかとの狙い通り風は弱まった。しかし、池と言えども水は無い。今年は雨が少ないのであろうか。

ここには、神津島特産種のイズノシマホシクサが繁殖していると案内板に書いてあるが、水は無いので駄目なのだろう。少し風が落ち着いたのもあって、池の側に在ったベンチに腰掛け、お菓子を口にする。気温は寒くは無いが風が強いので、この先も風に吹かれる事を見越して合羽を防寒具代わりに着込む。
15分ほど千代池で休憩した後、再び先に進む。すると、黒島展望山という高台に行く道があるが、先程の学生たちの声が聞こえて来た。

こんな強風の中、わざわざ高台に行ったのかと。自分は彼らとは逆の方向へと向かう。
この道は大変細く、藪漕ぎまでは行かないものの、足元のシダや背丈ほどある木に覆われて体の幅くらいしか無い道で、視界は拓けず長ソデ長ズボンでなければ気が滅入る道。この道を20分ほど進むと次第に視界が拓け、それまでの緑の景色から一転、一面の灰色の世界。表砂漠に足を踏み入れる。

この表砂漠は花崗岩が風化して出来た白い砂が、風や雨で窪地に溜って出来たのだという。

花崗岩は火山の地底奥深くで造られる。 それがこのように山頂一帯に見えているということは、 この山が火山活動していたのは太古の昔だということを示している。

長い年月の間に少しずつ崩れ、西暦838年に噴火した時などもあって、地底にあったはずの岩が露出して見えているのである。ここが日本であることを忘れそうな、独特の風景。「砂漠」というだけあって、砂はとてもキメ細かく乾いている。

少し砂地を登らなければならない場所があるのだが、 その砂が滑ったり足が砂にめり込んだりと歩きにくかったりする。10分ほど歩くと机と椅子がある広場があり、最高点に行く前にここで昼食にする。

そう言えば、先ほどの学生たち以来、人の姿は見えない。皆、風が強いので撤退してしまったのであろうか。
続いて表砂漠を後ろに見ながら天上山最高地点へ向かう。


この地点だけやや高い峰になっているので、再び上がる度に風が強まってくる。

最高地点へと立つ。

着いたものの、余りの強風で何かに摑まっていないと飛ばされそうな状態。
狭いピークでの強風の中の長逗留は危険と判断し、写真を一枚撮影したら撤退。次の目的地へ。
麓からも見えていた、天上山に刻まれた荒々しい崩壊の跡。

山の地図には神津沢とあり、目の前に切り立った崖を上から今見ている
。山頂付近に水が溜まって、それが崩落する事により、昔から村落が土砂災害にみまわれていたが、人工的に山を崩した跡である。
大正15年から行われた昭和46年にかけての治山工事により水が溜まらないようにし、完成した当時として国内最大級の砂防ダムのおかげで、土砂災害がなくなったという。
山が痛々しいようにも思えるが、 コンクリートで山の斜面を固めずに、ほぼ天上山の山頂部に近いこの場所に、ほぼ全ての資材を人力で搬入するという人の力には敬服する。
この時、やや雲が晴れて、その荒々しい崩落の先にある港を望めた
先程の神津沢の崖は天上山の火口縁でもある。反対側の窪みは、伊豆諸島の神々が集まって、水配りの会議をしたという不入ヶ沢(はいらないがさわ)である。

伊豆諸島が出来た後、神津島にて伊豆諸島の神々が島々の水を分ける為の会議を不入ヶ沢で行うと決まり会議を行い、次の朝に早い者順で水を分ける事になった。
朝になり、最初に着いたのが御蔵島の神様。続いて新島、八丈島、三宅島、大島の神様の順で到着して、最後に着いたのが利島の神様でしたが水が殆ど残っておらず、怒った利島の神様が不入ヶ沢の池で暴れて、その時に飛び散った水が神津島のあちこちに落ちた。その為、神津島にはあちこちで水が湧く様になった。
これが水分神話で、前浜海岸にあるモニュメントはこの神話を示している。そこから神の集う島=神集島=神津島となったと言われている。
不入ヶ沢は神聖な場所とされており、中に入ると出口が判らなくなって外に出られなくなるから絶対入ってはいけないとも言い伝えられて、人の立ち入りは禁止されている。

不入ヶ沢を見つつ、白島登山道の分岐になる。

ここからは前日に見た島の北部に在る神戸山を見下ろすポイントである。

ここから海を見下ろして下山に。振り返る度にそれまで歩いていた山頂部が離れていくのが惜しい気もする。

やがて木立の道に変わり、最後は急な石段に。






一時間ほどの下山で白島登山道の入口に出て車道に戻った。

ふと見上げると、先ほどまで居た天上山がもう遥か遠くに。

何度も何度も天上山を振り返る。
一つの山に白い砂漠や天然の池など見所が沢山あって、灌木や草原、大小さまざまな岩が連なり、また四季折々に咲く花や植物とともに、晴れた日には富士山まで見渡せる景観の素晴らしさ。本当に天上山という名がふさわしい山だなと思う。
神津沢の砂防ダム

来た時の道に戻る

こうして人里に戻ったのであるが、ここで問題が。
この日、神津島ではトライアスロン?な競技会が開かれていて、キャンプ場に通じるバスが運休しているというのだ。宿を予約してあるので、キャンプ場に戻ってテントを撤収してから宿に入ろうかと思っていたのだが。
歩いてキャンプ場まで戻れなくはないが、この疲れた足でキャンプ場に行って、撤収作業をし再び予約した宿がある所まで戻るのは難儀である。そこで、テントの撤収は翌朝に行う事にし、明日するはずだった郷土資料館の見学と土産の買物などをする事にする。
流人の墓地

神津島村郷土資料館は明治39年に建てられた旧役場の建物を保存し、隣に新しい建物を増設した資料館。

この施設の入館料もホワイトビーチきっぷに含まれている。
島の歴史と文化財を保存している訳だが、展示の中に明治32年の大火についての展示。水は豊富な神津とはいえ、水道が無い時代で集落が集中している中で起きた火事で、世帯数320の内、村役場を含む310世帯が焼失してしまった。旧役場の建物が出来たのが明治39年なので、この火事を受けてのものなのかもしれない。
展示は黒潮を通じて伝わる文化、という所に注目し、古代から現代までの神津島の歴史を知るための展示が見られたが、もう少し黒曜石の事や、流人や漂流などにも焦点を当てて欲しかった。
色々と土産を売っている所を見るのだが、どれも純然な神津島産の物が無い。いわゆる「販売者は地元だが、製造者が分からない」状態なのである。
一見するとそれらしい海産物の加工品なども、「神津島名物」というシールを貼ってあるだけ、というものが少なくない。あるのは焼酎の盛若とパッションフルーツくらいだろうか。売っている黒曜石も、妙に大きさが揃っていて、本当に神津産の物かは分からない。ここは残念な所であった。
あと、宿は夕食は無いので、食事をしようと思ったが飲食店が殆ど無いのも痛い。
買物の為に歩いていた時、だんだんと西に傾きつつある太陽が海を照らして美しく輝いた。

雲が多い日であったが、雲よりも低くなったので夕焼けが輝いたのだ。

この時、前浜に居た人々は、一様に夕焼けを見つめていた。

島に入ってから曇りがちな時間が多かったので、帰る前の日にこのような美しい輝きが見れて嬉しかった。


買物を済ませた後に予約した宿に入って荷物を置かせて頂く。

部屋に荷物は置かせて貰ったが、夜は所々で見掛けた「夜光虫鑑賞クルーズ」の貼り紙を見て予約していたので集合場所に向かう。
ライトアップされた水配神話の像

時間と共に参加者が集まり始め、ライフジャケットを着用して船に乗り込む。

船が港から出て10分ほどの沖合に来ると船の灯りを消し、その状態で船を旋回させると、水の中に蛍光色の輝きが無数に流れる。船に乗船している一同、感嘆の声を上げた。
月明かりも明々

海面をじっと見つめていると、何か光の中を漂っているかのような不思議な気分になってくる。
バケツで海水を汲んで、手で掻き回すると手の周りが輝く。
闇の中であったが、島の方に目を転じると、周りの洋々たる真っ暗な海の中で、島の灯りもまた人の営みが垣間見えて、妙に感動してしまった。

一時間ほどで船は港に戻り解散。

港近くに在るダイバーショップが夜のみ営業しているカフェに入り食事。

明日葉チャーハン
観光客だろうか、結構人が入っている。目の前の浜では花火を上げている人が居て、歓声が聞こえる。何となく、南の島に来た様なイメージの店だが、風は涼しく夏の終わりを感じさせる。この店も夏以外はやっていないのだから、シーズンオフの島の姿はどうなのだろうかと気になる所である。
明日葉入りのチャーハンを食べて宿に戻った。
宿に戻って風呂に入ろうとしたが、風呂は個人宅の風呂じゃないかと思う程の大きさで、しかもシャワーはお湯が出ない。登山する荷物以外はテントに置いて来てしまったので、身支度をするものが何もない。でも宿ならばあるだろうと思っていたのだが、アメニティとしてのタオルや浴衣、歯ブラシも言わなければ出してくれなかった。
う~ん、何の為に宿を取ったのだろうかと考えてしまった。これならテントに戻って温泉入れば良かった。山行で疲れていたのもあって、酒が入るとすぐ眠ってしまった。
朝起きて朝食時間になると、泊まっていた人が一堂に会する事になるが、ほぼ全部屋に人が居た様だ。
朝食の大広間には魚拓が色々と貼ってあったのだが、その中に夜光虫ツアーをやっていた船の名前があった。宿の人に聞いてみると娘の嫁ぎ先だという。魚もそこから入れているという。
そう言えば、宿の名前が漁船の名前みたいな所が多いなと思ってたが、漁業の傍らの民宿業である所が多いみたいで、魚介料理が好きな人なら堪らないのだろうなと。宿に対して飲食店が格段に少ないのもこの辺りなのかもしれない。
朝食を済ませて身支度を整えると、宿の人にキャンプ場まで送って頂いた。帰りの船の時間までにテントを撤収しなければならない。テントは無事で特に物が無くなっているという事も無かった。
しかし、ここで折悪く雨がパラついて来た。テントを片付けるには完全に乾かしたいのに。
幸い大きめのあずまやがあるので、そこで雨を避けつつ片付け作業。風も強くなってきて、乾かしているテントが煽られるなどもあったが、風で乾いたというのもあり、割と早めに片付けに成功。一息つくとバスの時間なのでバスに乗って港に向かう。
港の待合室は非常に込み合っている。

ホワイトビーチきっぷはこの日までの期限なので、この日に帰る人が多いのであろう。
改めて観光案内所で土産になる物はと見ていると、「神津島神々降臨伝説」というDVDを発見。島のPR用として、神津島の神話をフルCGで制作したという。
ややアヤしげな雰囲気もあるが、ここでなければ売ってないだろうとも思い購入。知人に「神津島どうだった?」と聞かれた時に渡してみるのにも使えるかもしれないかなと。
出航時間が近付き、乗船する。

乗り込む前に改めて天上山を望むと、山頂部は雲の中。

不入ヶ沢で神々が集まっているのだろうか。船の中はほぼ満席。
ジェットフォイル特有のエンジン音と共に船は岸を離れ島の緑が流れるようになると、また訪れたい、との名残惜しい気持ちを引き剥がすように、船は一気に加速するのであった。
写真まとめ
https://goo.gl/photos/RaWkKEaiMnmabdMr9
8500円で熱海から出航する高速船の往復券、島内のバス乗り放題、公共の温泉に入り放題、郷土資料館無料という特典があり、通常の運賃は片道で8200円ですのでかなりお得です。


熱海港を10:50に出港。

40分ほどで大島に停泊。

ここで機関に不具合が出たそうで10分ほど遅れたが、11:55に大島を出港。
30分ほどで利島、

鵜渡根島

新島を横目に見つつ、13時に神津島港に入港。


まずは港の観光案内所にてテント場の使用申請と島の情報収集。
それと、山に登る予定なので、その下山後は宿に泊まろうと民宿を手配してもらう。事前に行おうと思ったが、シーズンだからかどこも一杯だったのだ。運良く空いている宿があり、予約して貰う。
島に入って歩き出すと、まずは眼前に聳える天上山の荒々しい姿。

荒々しい天上山の対称的に優美な白浜が延びる前浜海岸。

「水配り神話」のモニュメントが立っています。


伊豆諸島の神々が神津島に集まって、如何に水を配分するかを協議したという
まずは郷土料理が食べたいなと、観光案内所で教えて貰った所へ向かった所、残念ながら本日貸切。30分ほど坂道を歩いたのがフイになったが、「佐久市友好の碑」というのを見掛けた。
それによると、平安時代中期の武将・藤原秀郷の子孫である藤原定国は伊豆諸島を領して神津島に館を構築した。その後、数世代が神津島に留まり、姓を神津氏とした。その後、甲斐国の武将・小笠原長清を守るため信濃の佐久地方に移ったという。
この縁で、神津島村は佐久市と姉妹都市交流があり、伊豆諸島と本州との関わりを示す一例であり、やはり来ないと知らない事はあるなと実感。
高台からの前浜海岸

島の集落を望む

島の中学校の校庭は芝生が美しい

集落の方へ向かう。神津島は港前の集落約4キロ平方メートルの地域に約800世帯、約1900人の人々が生活している。神津島に一軒というスーパーマーケットにて食材を色々と買い込むが、残念ながら地元の食材は少なかった。
ここでややにわか雨が。
再び歩いて個人商店のお店を覗くと、「盛若」という神津島の焼酎や、かなり希少な青ヶ島の焼酎をはじめ、食材も地元の物が多かった。
菓子パンなどは下田の物が多く、菓子パンの中には「きりんちゃん」というどう見ても「のっぽ」に似せたパンがあったので購入。

下田との定期船がこういう所に活きていると感じる。
そう言えば、店の人が聴いていたラジオもSBS静岡放送だった。
少し歩いてみると村内の道路は入り組んでおり、個人経営の商店が多く20〜30メートルごとに商店があり、島人口1900人にしては多いのでは、とも思えるくらい。各々が様々な物を扱っていて、業態分けが出来ない雑多な感じが面白い。

狭い路地の中を原付が走り回るが、案の定、ヘルメットを被ってない人が多い。

食事の第二候補にした中華料理店が開いていなかったので、神津島役場の近くにあったあずまやで、海を見ながら先程買ったパンやお惣菜などを食べ焼酎も少し頂く。

曇りがちで風もあるので涼しいくらい。
おたあジュリア顕彰碑

おたあジュリアは、秀吉の朝鮮の役の際に連れてこられた朝鮮人女性。
キリシタン大名の小西行長に身柄を引き渡され、後にキリスト教に改宗し「ジュリア」は洗礼名、「おたあ」は日本名を示す。
関ヶ原の戦いにて敗れた行長が処刑され小西家が没落すると、おたあの才気を見初めた徳川家康によって駿府城の大奥に召し上げられ、家康付きの侍女として側近く仕え寵愛を受けた。
しかし、慶長17年(1612年)の禁教令により駿府より追放され、神津島へと相次いで流罪となった。
食べ終わって再び歩き、島の鎮守である物忌奈命(ものいみなのみこと)神社にお参り。三日間、島に滞在するご挨拶。
この神社は出雲神話の大国主命の御子・事代主命が出雲の国譲りの後、出雲を出て伊豆諸島にやって来て島々を拓き、神津島の女神・阿波咩命(あわのめのみこと)との御子として生まれたのが物忌奈命である。

社殿は江戸中期の造りで唐破風が重厚な造り。

境内も掃き清められていて、式内社の風格があります。

しめ縄の張ってある木の洞

時折見かける奉納された神社内の砲弾


観光客が多い島だからでしょうか



神社の境内から延びる石段を降りると、そこは来た港の目の前。

バス停にてバスに乗り込み、バスは三分ほどでキャンプ場へ。

キャンプ場は静かな入り江である沢尻海岸にあり、トイレ、シャワー、炊事棟があり、万全の備え。ここが無料で使用できるとは。幕営していたのは5組ほどである。


観光案内所で前日は風が強かった事を聞いていたので、壁がある側にテントを張る。30分ほどで設営し、温泉へ向かう。

神津島温泉保養センターはバスで行けるがバスはもう運行が終了してしまった時間なので、10分ほど歩いて行く。この施設も元は大人800円であるが、ホワイトビーチきっぷで入り放題である。
内風呂と露天風呂があり、水着着用の露天風呂は大・小・展望風呂があり、自然の岩場を利用した大露天風呂は、100人は入れるという大きさで、海に面しており開放感は抜群。ただ、真っ暗なので景色は見えず眼鏡を外すと足元も見え辛いので、岩場を歩くのも危ない。故障しているらしく湯温がぬるく水着着用の為、余り気持ち良いとは言えない。明るい時に来たいかなと。
テント場に戻り、夜の海と他のキャンプ客がやってる花火を見つつ、スーパーで買ったお惣菜を食べ焼酎を飲んでいたらそのまま寝てしまう。初日終了である。
二日目。天気は良く、本当は天上山に登ろうとしたが、天気予報では昼から雨が降るというので、予定を変更して島内散策をする事に。
昨日、島内に在るパン屋さんで買ったパンを食べて、朝食を済ませた後、島の北側に向かって散策。


海岸には所々に天草を干している。

伊勢エビやとこぶしも豊富だそうだ。そう言えば、密漁を警告する看板も多い。

先日の温泉保養センター。

露天風呂が道路から見えるんですが。(水着着用だけど)

その先は覆い被さるかのような断崖のすぐ脇にある道路を歩く。


ここは大きな地震が今来たら海側にも山側にも逃げ場が無く怖いな・・・と思わせる。
港の周辺やテント場の辺りとは違って、この辺りは海岸も変化に富んだ流紋岩という岩の岩礁と松が連なり、見ていて飽きない。



一番先まで歩いて行く

流紋岩の中でも金雲母流紋岩という岩が日光を反射して輝くメッポー山という所。

岩山が亀の様な形をしている事から、亀山とも呼ばれたそうだが、実際に亀の産卵もあるという。

歩き始めて一時間ほど。ここには長浜キャンプ場があるが、誰もキャンプしている人は居ない。

静かなキャンプと海水浴に徹するなら良いが、市街地から離れているので、ある程度、食料などを準備しないとここでは大変だろう。
そしてここには阿波命神社がある。(が、始め気付かず通り過ぎてから気付く)


この神社は前日の物忌奈命神社に次ぐ式内社であるが、集落の側に在る物忌奈命神社に比べると、やや寂しい印象である。ただ、神社の社殿の様子などが、続日本後紀という文献の記述と一致している、古代神社の立地を今に伝える貴重な神社であるという。
阿波命は事代主の来島を祈り、この地で宴を開いて歓迎し、事代主が島を離れる時は、この地で水平線で見えなくなるまで別れを惜しんだという。
その事から、この長浜海岸には白砂と赤や黄色など色とりどりの玉石があり、別名「五色浜」とも言われるが、石を持ち去ると祟りがあるという。

定期船が

更に一時間ほど歩くと、海岸に人工の構造物が。近寄ってみると、レールが敷かれていた跡があった。

近くに案内板があるので、それを見ると、かつて採掘されていた抗火石という石材の運び出しを行っていた跡との事。

抗火石は新島の印象が強かったが、かつては神津島でも採掘されていたという。

抗火石は流紋岩の一種で、スポンジ状の構造から鋸や斧で容易に切断でき、その軽量性、耐火性、断熱性、耐酸性から多くの用途に使用されている。

その特性を利用し、過去には抗火石で作られた石の船も存在した。伊豆諸島以外ではイタリアのリーパリ島のみが採掘地である。
山側に崩落が著しい山があり神戸山というが、この山全体が抗火石であるという。

昭和17年に日産化学工業が採掘の為に施設を設けた。当時は道路が通じていなかったので、神戸山に支柱を設けて海まで索道を張り、山で採掘した石材をこの索道で運び、海側でトロッコに乗せ、運搬船に荷積みした。この湾には採石場で働く人々が多く住んでいた。
需要の減少により昭和30年にこの施設を用いた荷積みは行われなくなったが、島内で用いる住宅や道路の石垣などの石材として平成12年まで採石が行われていた。
坑火石の切り出し場から15分ほどで赤崎海水浴場。

ここは岩礁を渡れるように木道が整備されているのと、それを利用した海水浴場である。

この時も風が強く波もあったが、岩場に囲まれているので海水浴場は静かで珊瑚や小魚の大群が入ってきたりと魚影豊か。それを見る為かダイビングの人も多い。でもシュノーケリングでも見られそう。

岩場に遊歩道と共に櫓が組んであって、様々な高さから海に飛び込めるようになっている。



肌寒いので海水浴をしているのは10人程度だったが、海遊びには興味が無い私も、ここはもう少し暑い時期に来て海水浴をしたいと思わせる所です。

遊歩道を歩いていくと展望台があり、式根島、新島、利島と来た時に船から見た島々を眺めることが出来る。



ただ、海側で傷みもあるからか、通れない箇所もあり、行先に渡れない所もあった。

後で知ったが、昨年の伊豆大島での土砂災害の時の大雨では神津島も豪雨により所々で遊歩道が崩落してしまったという。

遊歩道が通じていなかったので車道のトンネルを抜けたが、その先のトンネルが行き止まりであった。

これも後で知ったが、平成12年の三宅島の噴火の際、神津島・新島・利島では震度五クラスの地震が頻発し、神津島では死者一名を出している。
その地震により、先の道路が神戸山の崩落に巻き込まれてしまった時から工事が止まっているとの事である。港の近くにあった公園には地震の碑があったのを思い出した。風光明媚ではあるが、昔から地震にも見舞われて来た島なのである。
その脇にあった湧き水

赤崎遊歩道のバス停からバスに乗り込み港の方へ戻る。二時間近くかけて歩いて来た道も戻るのは20分ほどである。
港のバス停で降りて、昨日閉まっていた中華料理の店で食事。
この週にあるトライアスロン?な競技会に参加する人が大勢居り、たくさん食べる人たちであった。
歩いている途中で見掛けたスナック・アニメイト



食事の後、このまま島の反対側である多幸湾へ向かおうと思ったが、バスの時間まで時間があるので高台にある図書館に向かう。
図書館がある高台からの眺め

島の図書館は新しいが、余り利用されていないのも感じた。確かに平日であるが、ご年配の人なども居ないのである。高台なので歩いて来るにはやや厳しいというのもあるのかもしれない。使われていないのがもったいないと感じた。
図書館からバス停へ向かう途中、与種神社という神社というより祠があった。

説明版には甘藷先生と呼ばれた青木昆陽を祀った神社で、サツマイモの普及により、島内でも飢餓の恐怖から救われた事でこの祠が建て祀られたという。全国的にサツマイモの普及を讃える神社はあるが、この地でも見つける事が出来、非常に嬉しかった。
バス停から多幸湾へ向かうバスに乗り込む。図書館に居た時は良い天気であったが、ここに来て急に曇りとなり、雨もポツポツ落ちて来た。
こちらのバス路線の運転手さんは話し好きなのか、他の乗客の人と盛んに話をしていた。更に、景観が良い所などでは減速して見所を案内するなど、サービス旺盛である。

神津島空港

バスは神津島空港を経由するのだが、その途中にあった三浦湾の景色が素晴らしく減速してくれたものの、停車では無いので写真を撮れなかったのが残念。

こちらも20分ほどで多幸湾へ到着。多幸湾は神津島港の反対側であるので、強風や波浪によって神津島港に船が停泊できない場合は、こちらが発着になる事がある。
港と言っても周囲には商店・民家らしき物は何も無く、自販機だけがポツンとあるだけ。港の待合所になる建物があるが、利用されていないので閉まっている。
多幸湾の待合所の脇にはカジキマグロに乗った人の像が立っている。

これは神津島村の村の魚がカジキマグロであるからで、伊豆諸島の中でも漁業が盛んな島であり、中でもカジキマグロ漁が盛んである事からであろう。
曇りで雨粒が落ちている事もあって人気は殆ど無いが、白く長く伸びる素晴らしい砂浜と、天上山の山頂近くから海にまで崩落している崩れ地形は迫力抜群である。




その先には砂糠崎という黒曜石が露出している岬がある。


そして、海岸のすぐ側には都内でも有数の湧水が湧出しているなど、神津島の特徴が全てこの地に集まってると言えよう。
港方面に戻るバスまで時間が有るので、周辺を散策。散策路として港の方に抜ける山道もあるが、いつ雨が降りだすかわからないので、周辺を歩くにとどめる。





特に見るべきものなどは無いが、多幸湾キャンプ場があるので覗いてみると、コチラは有料であるものの、管理者が常駐しており冷蔵庫や荷物や貴重品の預かり、炊事場のみならずお風呂付など至れり尽くせりのキャンプ場である。
バスが発車する時間になったのでバスに乗り込み、再びスーパー近くのバス停で降りる。
先日は入らなかった百円ショップに入ったら色々とキャンプ用品もあった。その時、炊事場に炭が捨てられていた事を思い出し、
「これでバーベキュー出来るんじゃね?」
と思い立ち、百円ショップで網や調味料を、スーパーで食材を購入。
他の商店でも食料品を購入していたらバスの時間が過ぎてしまい、歩いてキャンプ場まで戻る事に。
途中の岩穴にて雨宿り


しかも折悪く雨が強く降り始め、靴はずぶ濡れ、中まで水が浸み込み精神的にヘコみながらもテントへ戻る。
すると、近くの旅館に泊まっている団体さんが炊事場を使っているので、先に温泉保養センターに行く事にする。風呂から上がると雨はかなり強くなり傘を差しても濡れるほどに見える。しかし閉館時間が近付きつつあり、腹の減り具合もかなりであるので、雨の中をテント場へ戻る。
もう団体さんは居ないものの、今度は風が強くなり、屋根がある炊事場も雨が吹き込んでくる。そんな事もあって中々火が点かず、食材に火が通るまでかなりの時間を要してしまい疲れた・・・。
朝起きると、昨夜の雨でテントの床面に水が浸み込み、寝袋も濡れてしまってやや気分が落ち込み。
しかし、空を見上げると雲が多いものの青空ものぞかせ、登山の気分は高まった。
コンロに火を点けて水を沸かし、レトルトの粥を温めて熱いお茶を淹れた。朝食も体温を上げようと、温かい物を食べて気分を高める。
登山の準備をし、朝一番のバスに乗り込んで港へ。神津島の天上山は標高574メートルであるが、実質、海抜0mからの登山と言える。島に降り立った時も感じたが、正しく壁のように見える。本当にこの山を登れるのだろうかという不安感もよぎる。
島の中心部である地区を抜けて住宅地となり、天上山方面には「黒島口」と「白島口」という2つの登山口の分岐点がある。今回は最短距離の「黒島口」を選ぶ。
更に標高が高くなっていくと、次第に緑が濃くなっていく。


港から歩き始めて一時間、ここで車道は途切れ登山口となる。
登山口近くに在った風穴


火山らしい
その先に進んでいくと、眼下に昨日見た多幸湾や高処山、秩父山が見える。


改めて地図を見ると、どうやら行き過ぎてしまったようだ。昨日、雨で無かったら多幸湾から港方面へと歩こうと思っていた道だったらしい。戻りつつ、注意深く山側を観察して歩くと、登山道発見。木々で良く見えなかったので見過ごしていた様だ。


この黒島口登山道は神津島の中心集落を見下ろしつつ登れる道である。

序盤はシダが生い茂り歩きづらい。そう感じても、第一歩を踏み出さなければ登山は出来ない。無心になって足を進める。

登山道には「〇合目」との表記が定期的に示されて設置されており、それを目安にして休憩を入れる。次第に歩きやすい道になり、高みを増すたびに海が広く見えてくる。結構な急登だが景色が綺麗なので疲れを感じない。どこで立ち止まっても素晴らしい展望だ。
登山道を30分ほど歩き始めると、学生らしき若者たち15人ほどが追い付きそうだったので先に行かせた。彼らの軽装が気になる。
この頃までは天気は良く青空も見えていたのだが、次第に雲も見え始め、山頂が見えなくなった。

標高が上がってくると雲の中になり、下界の様子も見えなくなった。

学生たちの声は聞こえていたが、姿も見えなくなった。山の様子も木々の緑は少なくなり、灰色の岩の方が多い色彩になる。

この8合目付近に在ったのが、「鬼たちの力比べ」という伝説を示した案内板。力自慢の鬼達が天から降りて来て、ここで50メートルある石を投げて力くらべをしたという、伝説が残っている。
それまで、前述の学生たち以外に人を見ていなかったが、降りて来た人が居た。降りて来た人が「まだ上に行くの?」と聞いて来た。十合目から先がとんでもない強風なのだという。
ここまではまだ風は然程では無かったが、上がる度に風を感じ、15分ほど歩くと十合目の標柱が見えてきた。
十合目の標柱を過ぎたとはいえ 台形型の天上山の門に立ったに過ぎず、ここがゴールではない。むしろ天上山の魅力はこれからである。
十合目の標柱を超えると風がとんでもない強さになり、体感では20m以上はあるのではなかろうか。撤退もやや思い浮かんだが、雨は降っていないのと、この先はやや窪みであるので、風も幾分弱まるかと思い先に進む事にする。
まずやって来たのは、オロシャの石塁と呼ばれる文政の石積跡。
江戸末期、外国船籍の船が日本各地に出没するようになったため、幕府は伊豆諸島の島民に鉄砲と槍を備えさせ、更に外国人が島に上陸した時、天上山に引き寄せて戦えるように石積の防塁を約300mにわたって築いたもの。と説明がある。ただ、実際は石材を切り出していた頃の名残だという。
しかし、ここは先程居た所よりも風が強く崖の側なので、写真を一枚撮っただけで早々と引き返す。晴れていればかなりの展望であっただろうなぁ。
次に千代池(せんだいいけ)へ向かう。天上山の頂上台地には、火口跡に雨水が溜まって出来た幾つかの池があり、中でも千代池は一番大きい池である。
池であるからやや窪みであろうと思い、風も弱まるかとの狙い通り風は弱まった。しかし、池と言えども水は無い。今年は雨が少ないのであろうか。

ここには、神津島特産種のイズノシマホシクサが繁殖していると案内板に書いてあるが、水は無いので駄目なのだろう。少し風が落ち着いたのもあって、池の側に在ったベンチに腰掛け、お菓子を口にする。気温は寒くは無いが風が強いので、この先も風に吹かれる事を見越して合羽を防寒具代わりに着込む。
15分ほど千代池で休憩した後、再び先に進む。すると、黒島展望山という高台に行く道があるが、先程の学生たちの声が聞こえて来た。

こんな強風の中、わざわざ高台に行ったのかと。自分は彼らとは逆の方向へと向かう。
この道は大変細く、藪漕ぎまでは行かないものの、足元のシダや背丈ほどある木に覆われて体の幅くらいしか無い道で、視界は拓けず長ソデ長ズボンでなければ気が滅入る道。この道を20分ほど進むと次第に視界が拓け、それまでの緑の景色から一転、一面の灰色の世界。表砂漠に足を踏み入れる。

この表砂漠は花崗岩が風化して出来た白い砂が、風や雨で窪地に溜って出来たのだという。

花崗岩は火山の地底奥深くで造られる。 それがこのように山頂一帯に見えているということは、 この山が火山活動していたのは太古の昔だということを示している。

長い年月の間に少しずつ崩れ、西暦838年に噴火した時などもあって、地底にあったはずの岩が露出して見えているのである。ここが日本であることを忘れそうな、独特の風景。「砂漠」というだけあって、砂はとてもキメ細かく乾いている。

少し砂地を登らなければならない場所があるのだが、 その砂が滑ったり足が砂にめり込んだりと歩きにくかったりする。10分ほど歩くと机と椅子がある広場があり、最高点に行く前にここで昼食にする。

そう言えば、先ほどの学生たち以来、人の姿は見えない。皆、風が強いので撤退してしまったのであろうか。
続いて表砂漠を後ろに見ながら天上山最高地点へ向かう。


この地点だけやや高い峰になっているので、再び上がる度に風が強まってくる。

最高地点へと立つ。

着いたものの、余りの強風で何かに摑まっていないと飛ばされそうな状態。
狭いピークでの強風の中の長逗留は危険と判断し、写真を一枚撮影したら撤退。次の目的地へ。
麓からも見えていた、天上山に刻まれた荒々しい崩壊の跡。

山の地図には神津沢とあり、目の前に切り立った崖を上から今見ている
。山頂付近に水が溜まって、それが崩落する事により、昔から村落が土砂災害にみまわれていたが、人工的に山を崩した跡である。
大正15年から行われた昭和46年にかけての治山工事により水が溜まらないようにし、完成した当時として国内最大級の砂防ダムのおかげで、土砂災害がなくなったという。
山が痛々しいようにも思えるが、 コンクリートで山の斜面を固めずに、ほぼ天上山の山頂部に近いこの場所に、ほぼ全ての資材を人力で搬入するという人の力には敬服する。
この時、やや雲が晴れて、その荒々しい崩落の先にある港を望めた
先程の神津沢の崖は天上山の火口縁でもある。反対側の窪みは、伊豆諸島の神々が集まって、水配りの会議をしたという不入ヶ沢(はいらないがさわ)である。

伊豆諸島が出来た後、神津島にて伊豆諸島の神々が島々の水を分ける為の会議を不入ヶ沢で行うと決まり会議を行い、次の朝に早い者順で水を分ける事になった。
朝になり、最初に着いたのが御蔵島の神様。続いて新島、八丈島、三宅島、大島の神様の順で到着して、最後に着いたのが利島の神様でしたが水が殆ど残っておらず、怒った利島の神様が不入ヶ沢の池で暴れて、その時に飛び散った水が神津島のあちこちに落ちた。その為、神津島にはあちこちで水が湧く様になった。
これが水分神話で、前浜海岸にあるモニュメントはこの神話を示している。そこから神の集う島=神集島=神津島となったと言われている。
不入ヶ沢は神聖な場所とされており、中に入ると出口が判らなくなって外に出られなくなるから絶対入ってはいけないとも言い伝えられて、人の立ち入りは禁止されている。

不入ヶ沢を見つつ、白島登山道の分岐になる。

ここからは前日に見た島の北部に在る神戸山を見下ろすポイントである。

ここから海を見下ろして下山に。振り返る度にそれまで歩いていた山頂部が離れていくのが惜しい気もする。

やがて木立の道に変わり、最後は急な石段に。






一時間ほどの下山で白島登山道の入口に出て車道に戻った。

ふと見上げると、先ほどまで居た天上山がもう遥か遠くに。

何度も何度も天上山を振り返る。
一つの山に白い砂漠や天然の池など見所が沢山あって、灌木や草原、大小さまざまな岩が連なり、また四季折々に咲く花や植物とともに、晴れた日には富士山まで見渡せる景観の素晴らしさ。本当に天上山という名がふさわしい山だなと思う。
神津沢の砂防ダム

来た時の道に戻る

こうして人里に戻ったのであるが、ここで問題が。
この日、神津島ではトライアスロン?な競技会が開かれていて、キャンプ場に通じるバスが運休しているというのだ。宿を予約してあるので、キャンプ場に戻ってテントを撤収してから宿に入ろうかと思っていたのだが。
歩いてキャンプ場まで戻れなくはないが、この疲れた足でキャンプ場に行って、撤収作業をし再び予約した宿がある所まで戻るのは難儀である。そこで、テントの撤収は翌朝に行う事にし、明日するはずだった郷土資料館の見学と土産の買物などをする事にする。
流人の墓地

神津島村郷土資料館は明治39年に建てられた旧役場の建物を保存し、隣に新しい建物を増設した資料館。

この施設の入館料もホワイトビーチきっぷに含まれている。
島の歴史と文化財を保存している訳だが、展示の中に明治32年の大火についての展示。水は豊富な神津とはいえ、水道が無い時代で集落が集中している中で起きた火事で、世帯数320の内、村役場を含む310世帯が焼失してしまった。旧役場の建物が出来たのが明治39年なので、この火事を受けてのものなのかもしれない。
展示は黒潮を通じて伝わる文化、という所に注目し、古代から現代までの神津島の歴史を知るための展示が見られたが、もう少し黒曜石の事や、流人や漂流などにも焦点を当てて欲しかった。
色々と土産を売っている所を見るのだが、どれも純然な神津島産の物が無い。いわゆる「販売者は地元だが、製造者が分からない」状態なのである。
一見するとそれらしい海産物の加工品なども、「神津島名物」というシールを貼ってあるだけ、というものが少なくない。あるのは焼酎の盛若とパッションフルーツくらいだろうか。売っている黒曜石も、妙に大きさが揃っていて、本当に神津産の物かは分からない。ここは残念な所であった。
あと、宿は夕食は無いので、食事をしようと思ったが飲食店が殆ど無いのも痛い。
買物の為に歩いていた時、だんだんと西に傾きつつある太陽が海を照らして美しく輝いた。

雲が多い日であったが、雲よりも低くなったので夕焼けが輝いたのだ。

この時、前浜に居た人々は、一様に夕焼けを見つめていた。

島に入ってから曇りがちな時間が多かったので、帰る前の日にこのような美しい輝きが見れて嬉しかった。


買物を済ませた後に予約した宿に入って荷物を置かせて頂く。

部屋に荷物は置かせて貰ったが、夜は所々で見掛けた「夜光虫鑑賞クルーズ」の貼り紙を見て予約していたので集合場所に向かう。
ライトアップされた水配神話の像

時間と共に参加者が集まり始め、ライフジャケットを着用して船に乗り込む。

船が港から出て10分ほどの沖合に来ると船の灯りを消し、その状態で船を旋回させると、水の中に蛍光色の輝きが無数に流れる。船に乗船している一同、感嘆の声を上げた。
月明かりも明々

海面をじっと見つめていると、何か光の中を漂っているかのような不思議な気分になってくる。
バケツで海水を汲んで、手で掻き回すると手の周りが輝く。
闇の中であったが、島の方に目を転じると、周りの洋々たる真っ暗な海の中で、島の灯りもまた人の営みが垣間見えて、妙に感動してしまった。

一時間ほどで船は港に戻り解散。

港近くに在るダイバーショップが夜のみ営業しているカフェに入り食事。

明日葉チャーハン
観光客だろうか、結構人が入っている。目の前の浜では花火を上げている人が居て、歓声が聞こえる。何となく、南の島に来た様なイメージの店だが、風は涼しく夏の終わりを感じさせる。この店も夏以外はやっていないのだから、シーズンオフの島の姿はどうなのだろうかと気になる所である。
明日葉入りのチャーハンを食べて宿に戻った。
宿に戻って風呂に入ろうとしたが、風呂は個人宅の風呂じゃないかと思う程の大きさで、しかもシャワーはお湯が出ない。登山する荷物以外はテントに置いて来てしまったので、身支度をするものが何もない。でも宿ならばあるだろうと思っていたのだが、アメニティとしてのタオルや浴衣、歯ブラシも言わなければ出してくれなかった。
う~ん、何の為に宿を取ったのだろうかと考えてしまった。これならテントに戻って温泉入れば良かった。山行で疲れていたのもあって、酒が入るとすぐ眠ってしまった。
朝起きて朝食時間になると、泊まっていた人が一堂に会する事になるが、ほぼ全部屋に人が居た様だ。
朝食の大広間には魚拓が色々と貼ってあったのだが、その中に夜光虫ツアーをやっていた船の名前があった。宿の人に聞いてみると娘の嫁ぎ先だという。魚もそこから入れているという。
そう言えば、宿の名前が漁船の名前みたいな所が多いなと思ってたが、漁業の傍らの民宿業である所が多いみたいで、魚介料理が好きな人なら堪らないのだろうなと。宿に対して飲食店が格段に少ないのもこの辺りなのかもしれない。
朝食を済ませて身支度を整えると、宿の人にキャンプ場まで送って頂いた。帰りの船の時間までにテントを撤収しなければならない。テントは無事で特に物が無くなっているという事も無かった。
しかし、ここで折悪く雨がパラついて来た。テントを片付けるには完全に乾かしたいのに。
幸い大きめのあずまやがあるので、そこで雨を避けつつ片付け作業。風も強くなってきて、乾かしているテントが煽られるなどもあったが、風で乾いたというのもあり、割と早めに片付けに成功。一息つくとバスの時間なのでバスに乗って港に向かう。
港の待合室は非常に込み合っている。

ホワイトビーチきっぷはこの日までの期限なので、この日に帰る人が多いのであろう。
改めて観光案内所で土産になる物はと見ていると、「神津島神々降臨伝説」というDVDを発見。島のPR用として、神津島の神話をフルCGで制作したという。
ややアヤしげな雰囲気もあるが、ここでなければ売ってないだろうとも思い購入。知人に「神津島どうだった?」と聞かれた時に渡してみるのにも使えるかもしれないかなと。
出航時間が近付き、乗船する。

乗り込む前に改めて天上山を望むと、山頂部は雲の中。

不入ヶ沢で神々が集まっているのだろうか。船の中はほぼ満席。
ジェットフォイル特有のエンジン音と共に船は岸を離れ島の緑が流れるようになると、また訪れたい、との名残惜しい気持ちを引き剥がすように、船は一気に加速するのであった。
写真まとめ
https://goo.gl/photos/RaWkKEaiMnmabdMr9
2015年07月22日
7月29日講演 「巨船の航跡 核の時代の二律背反(アンビバレンス)」 沼津市 高嶋酒造にて
7月29日18時半より講演致します。
内容は「巨船の航跡 核の時代の二律背反(アンビバレンス)」です。

(日本に原子力を導入しようと動いた中曽根康弘と正力松太郎)
広島・長崎の原爆投下に次ぐ第五福竜丸事件。日本は核兵器による災厄を受けながらも、平和的に技術を用いる事で敗戦による混乱を克服しようと考えた。
科学技術が全ての人を幸せにすると考えられ、原子力が導入されていった経緯をお話しします。
「戦後社会・核開発・ビキニ事件・原子力発電・技術史・原発問題」に関心がある方にオススメ。
参加費:700円。
時間:18時30分から
開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて
※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)
※自由参加ですが、問い合わせ等は高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)
内容は「巨船の航跡 核の時代の二律背反(アンビバレンス)」です。
(日本に原子力を導入しようと動いた中曽根康弘と正力松太郎)
広島・長崎の原爆投下に次ぐ第五福竜丸事件。日本は核兵器による災厄を受けながらも、平和的に技術を用いる事で敗戦による混乱を克服しようと考えた。
科学技術が全ての人を幸せにすると考えられ、原子力が導入されていった経緯をお話しします。
「戦後社会・核開発・ビキニ事件・原子力発電・技術史・原発問題」に関心がある方にオススメ。
参加費:700円。
時間:18時30分から
開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて
※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)
※自由参加ですが、問い合わせ等は高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)
2015年07月17日
千駄木空間 Tシャツ展はじまりました
東京都文京区千駄木のギャラリー・千駄木空間でのTシャツ展が始まりました。

会場は「へび道」という小川の暗渠の路地。少し分かりにくい(私も二回ばかりぐるぐる廻りました)ですが、隠れ家感のあるお店が所々に在ります。
私が搬入に尋ねた時は、既に他の人の搬入が終わっていて、展示は空いている所でしたが、入り口から入って正面に見える所なので、余り物に福でしょうか。

この企画の宣伝がてら、9日に秋葉原のシャッツキステという店で行われたTシャツのプレゼン会に参加して来ました。
この店は以前訪れた事はあったのですが、こういった企画に参加するのは初めて。ほぼ新参という事で、扉を開けるのも少し勇気が要りましたが、思い切っての参加です。
10人位かな~と思ってましたが30人ほどで席は殆ど埋まり、ほぼ全ての人が持ち寄ったTシャツについてプレゼンしていました。
普段の歴史講座では大勢でもそれほど緊張しませんが、自分の番になった時、とても緊張しましたが、思った以上に反応があったので来て(着て?)良かったと思いました。多くの人にTシャツ展の案内が出来て良かった・・・。
それぞれがそのTシャツにまつわる嬉しかったことや、悲しい思い出、とてもレアなもの、この時初めて封を開けたもの、ちょっと着るには躊躇するものなどなど・・・これだけ見ても、単なる衣服の範疇を超えていると思います。
私がTシャツのデザインを手掛けるようになったのも、コミュニケーションツールとなるのではなかろうか、と思ったからです。それをきっかけに余り詳しくなくても地域の歴史を伝える事が出来れば、と思ったのが狙いです。
店が閉まるまで居たかったですが、帰りの時間もあり途中で撤退したのが口惜しいです。
それでは、千駄木空間のTシャツ展、私以外にも様々なデザインがありますので、どうぞ足をお運びください。

会場は「へび道」という小川の暗渠の路地。少し分かりにくい(私も二回ばかりぐるぐる廻りました)ですが、隠れ家感のあるお店が所々に在ります。
私が搬入に尋ねた時は、既に他の人の搬入が終わっていて、展示は空いている所でしたが、入り口から入って正面に見える所なので、余り物に福でしょうか。

この企画の宣伝がてら、9日に秋葉原のシャッツキステという店で行われたTシャツのプレゼン会に参加して来ました。
この店は以前訪れた事はあったのですが、こういった企画に参加するのは初めて。ほぼ新参という事で、扉を開けるのも少し勇気が要りましたが、思い切っての参加です。
10人位かな~と思ってましたが30人ほどで席は殆ど埋まり、ほぼ全ての人が持ち寄ったTシャツについてプレゼンしていました。
普段の歴史講座では大勢でもそれほど緊張しませんが、自分の番になった時、とても緊張しましたが、思った以上に反応があったので来て(着て?)良かったと思いました。多くの人にTシャツ展の案内が出来て良かった・・・。
それぞれがそのTシャツにまつわる嬉しかったことや、悲しい思い出、とてもレアなもの、この時初めて封を開けたもの、ちょっと着るには躊躇するものなどなど・・・これだけ見ても、単なる衣服の範疇を超えていると思います。
私がTシャツのデザインを手掛けるようになったのも、コミュニケーションツールとなるのではなかろうか、と思ったからです。それをきっかけに余り詳しくなくても地域の歴史を伝える事が出来れば、と思ったのが狙いです。
店が閉まるまで居たかったですが、帰りの時間もあり途中で撤退したのが口惜しいです。
それでは、千駄木空間のTシャツ展、私以外にも様々なデザインがありますので、どうぞ足をお運びください。
2015年07月09日
千駄木空間 Tシャツ展へ出展
来る7月15日から20日に掛けて、東京・千駄木のギャラリー・千駄木空間さんで行われる「千駄木商店」に出展いたします。

千駄木空間さんはオープンした2006年から夏にデザインTシャツの展示を行っており、年々出展者が増えている作品展です。

千駄木商店には私の他に20名の方が出展しますが、作家紹介の一覧を見ても私とは違うアーティスティックな方たちばかり。そんな中で私の「歴史を伝えるデザイン」は作家の人達および来場する人たちにどれだけ通用するのか、不安でもあり楽しみでもあります。
私は初日の15日と最終日の20日終り際しか居ませんが、どうぞ足をお運びください。

千駄木空間さんはオープンした2006年から夏にデザインTシャツの展示を行っており、年々出展者が増えている作品展です。

千駄木商店には私の他に20名の方が出展しますが、作家紹介の一覧を見ても私とは違うアーティスティックな方たちばかり。そんな中で私の「歴史を伝えるデザイン」は作家の人達および来場する人たちにどれだけ通用するのか、不安でもあり楽しみでもあります。
私は初日の15日と最終日の20日終り際しか居ませんが、どうぞ足をお運びください。
2015年07月07日
本日講演 「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」 沼津市 Lot.nにて
本日18時半から沼津市のLot.nにて行います。
内容は「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」です。
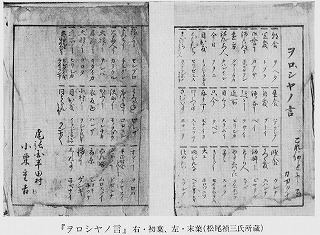
(重吉がまとめたロシア語単語集「ヲロシャノ言」)
江戸時代、駿河湾を航行していた尾張と伊豆の船乗りたち。
彼らは暴風に巻き込まれ、一年半にも及んで太平洋を漂い、遂にはアメリカ大陸にまで到達した。彼らの漂流の苦闘と帰国に便宜を図ったイギリス人・ロシア人船乗りの人道精神の道のりを語ります。
「江戸時代・海運・危機管理・漂流・異文化交流」に関心がある方におすすめ。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです
)
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接来場ください。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです
)
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接来場ください。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」です。
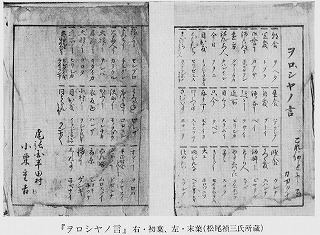
(重吉がまとめたロシア語単語集「ヲロシャノ言」)
江戸時代、駿河湾を航行していた尾張と伊豆の船乗りたち。
彼らは暴風に巻き込まれ、一年半にも及んで太平洋を漂い、遂にはアメリカ大陸にまで到達した。彼らの漂流の苦闘と帰国に便宜を図ったイギリス人・ロシア人船乗りの人道精神の道のりを語ります。
「江戸時代・海運・危機管理・漂流・異文化交流」に関心がある方におすすめ。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです
)
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接来場ください。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです
)
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接来場ください。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。







