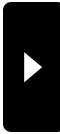no">
2015年09月28日
10月11日講演 「果ての島の物語 玉置半右衛門と欲望の渡り鳥たち」 散歩かふぇ ちゃらぽこにて
10月11日15時より散歩かふぇ ちゃらぽこにて講演致します。
内容は「
果ての島の物語 玉置半右衛門と欲望の渡り鳥たち」です。

(鳥島空撮)
外国人の冒険商人たちに触発された玉置半右衛門は、絶海の孤島・鳥島に分け入り群れ飛ぶアホウドリを捕まえ巨万の富を得る事に成功する。彼に触発された山師めいた商人たちは、無人島を見つけては事業を展開して行く。
日本の版図が拡がりゆく時代、玉置商会という会社を通じて、開拓の負の一面を語ります。
「明治時代・無人島開拓・伊豆諸島、琉球地域・プランテーション・アホウドリ」に関心がある方にオススメ。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「
果ての島の物語 玉置半右衛門と欲望の渡り鳥たち」です。

(鳥島空撮)
外国人の冒険商人たちに触発された玉置半右衛門は、絶海の孤島・鳥島に分け入り群れ飛ぶアホウドリを捕まえ巨万の富を得る事に成功する。彼に触発された山師めいた商人たちは、無人島を見つけては事業を展開して行く。
日本の版図が拡がりゆく時代、玉置商会という会社を通じて、開拓の負の一面を語ります。
「明治時代・無人島開拓・伊豆諸島、琉球地域・プランテーション・アホウドリ」に関心がある方にオススメ。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2015年09月26日
10月6日講演 「和魂の才 成熟社会の江戸技術」 沼津市 Lot.nにて
10月6日18時半から沼津市のLot.nにて行います。
内容は「和魂の才 成熟社会の江戸技術」です。

蘭学発展の契機となった「解体新書」
明治維新後の「文明開化」。進んだ技術を取り入れることによって近代化を図る試みは各国で行われたが、急速な社会変革に順応できたのは日本だけであった。
明治の近代化政策以前には日本に「文明」は無かったのか。その下地となった江戸時代の科学技術についてお話しします。
「産業史・江戸時代・科学史・外交史」に関心がある方におすすめ。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです
)
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
参加は自由です。Lot.nさんへ直接来場ください。
変更や中止の問い合わせ、申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへお問い合わせください
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「和魂の才 成熟社会の江戸技術」です。

蘭学発展の契機となった「解体新書」
明治維新後の「文明開化」。進んだ技術を取り入れることによって近代化を図る試みは各国で行われたが、急速な社会変革に順応できたのは日本だけであった。
明治の近代化政策以前には日本に「文明」は無かったのか。その下地となった江戸時代の科学技術についてお話しします。
「産業史・江戸時代・科学史・外交史」に関心がある方におすすめ。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです
)
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
参加は自由です。Lot.nさんへ直接来場ください。
変更や中止の問い合わせ、申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへお問い合わせください
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2015年09月25日
ホントに歩く東海道ウォーク 茅ヶ崎~大磯
※この記事は2014年9月の記事を再編集した物です。
お世話になっている「散歩かふぇ ちゃらぽこ」さんの企画「ホントに歩く東海道ウォーク 茅ヶ崎~大磯」に参加しました。
自分は街歩きをするに当たって街道筋は目安にしますが、街道を歩く事を目的としている訳では無いのもあって、東海道歩きは「品川~川崎・神奈川~藤沢・小田原~府中」など小間切れになっていました。
そこで、今回の企画は歩いていない茅ヶ崎~大磯を歩く企画という事で、参加です。

生憎の雨。そこそこ風も有る中、スタートです。

駅界隈は多少、歩いた事あります。
駅前から国道一号線に出て、ここから東海道を西へ進む。
観光案内所の前に居たキャラクター。

「えぼし麻呂」というらしい。茅ヶ崎に住む貴族だそうで、茅ヶ崎海岸沖の烏帽子岩からであろう。
樹齢200年超のクロマツ。

江戸時代の旅人もこの松を見たのであろう。
平成21年に枯死してしまったとか。
色々と話題になってる湘南クッキーの自販機

途中にあった竹細工の店

第六天神社

7月海の日に行われる浜降祭は、 神奈川県の民俗資料として無形文化財に指定され、茅ヶ崎海岸に近郷より三十数基神輿が集まる祭典との事。
三猿や道祖神の石碑

鉄工所のなかなかセンスある花壇が。

なかなか聞かないキャッチですね。

ナゾな落書き・・・ヘルメット?

南湖の左富士

左富士は富士市の吉原宿に向かう途中の所は知っていましたがココにも。
ココは富士山の真東に当たり、やや北西に向かう道となる事で「左」に富士がある。
南湖の左富士の側に鶴嶺八幡宮の鳥居。

東海道からはやや外れるが、八幡宮に向かう。
鶴嶺八幡宮へ向かう。

相模国茅ヶ崎の総社として往古より八幡信仰の本地として名高い。また鶴嶺八幡宮によると、源氏が関東へ進出する際、創建した最初の氏社という。





普段は水が満たされている神池ですが、この日は全く無かったです。


見事な参道

この並木は江戸時代に朝恵上人という八幡宮別当の僧侶が、当地の地頭と共に整備したという。
女護ヶ石

女性の守護神として、この石を撫でた後、体の良くない部分を撫でると良くなるという。

神社には珍しい鐘が。

習合時代の名残か。
御神木としてのイチョウ


かわらけ投げ

この石に当てる

崖などの高い所や海などではかわらけ投げやった事ありますが、こんな近い距離は初めて見ました
拝殿

針塚

がん封じ石

ここも女護ヶ石の様に、この石を撫でた後、体の良くない部分を撫でると良くなるという。
こういった石も神社としては珍しい。
末社の淡島神社

女護ヶ石はこの淡島社の関係でしょうか。
鶴嶺八幡宮から再び東海道へ。
神明社

この神社の境内にある晴明井戸の碑

安倍晴明が東国に赴いた際、喉を潤した井戸があったという。
東海道名物・でかまん菓子舗さんへ

一番大きいのは30センチ弱

大きいから味も大味・・・と言う事は無く、丁寧なこしあん。美味しく頂きました。

他の種類のお菓子も購入しました。
国指定史跡・相模川橋脚跡

鎌倉時代の御家人・稲毛重成が架橋した。その際に源頼朝が渡り初めの時に落馬し、死亡する傷を作ってしまった曰くつきの場所である。
時は大正12年の関東大震災。地震により水田から鎌倉時代の橋脚が姿を現し、調査の結果、史跡に指定された。
史跡としての重要性に加え、関東大震災の地震状況を示す天然記念物としても重要な史跡である。
そして相模川を渡ると平塚市に。

この辺りから風雨が強くなり、全身ずぶぬれに。ツラい。
橋を越えた先に在る陸軍架橋記念碑

関東大震災によって橋が落橋し、交通が寸断された。9月17日に陸軍の工兵部隊により架橋工事が行われた。10月3日に完成し、その事績を讃えた碑である。
丁髷塚

1838年、寒川神社の神輿が春に大磯で行われる国府祭に渡御した帰りに、一ノ宮の寒川神社の氏子と四ノ宮の前鳥神社の氏子とが相模川の渡し場で争いを起こし、寒川神社の御輿が川に落ちて行方不明となった。
争いは裁判となり、代官・江川英龍は前鳥神社の氏子16名に打首断罪の判決を下したが、処刑の日に代官はその丁髷だけを斬り落とし、打首に代えたという。これが丁髷塚である。
一里塚跡

日本橋から15番目の一里塚。
たまたま通り掛かった所にあった乳業メーカー・守山乳業の工場

門のすぐ内側に、創業者らしい銅像が有ったので見てみる。


調べたところ、創業は1918年1月と90年以上の歴史を持つ老舗である。
大正9年12月には日本で初めてコーヒー牛乳を製造した会社でもある。

続けて国産初の無糖練乳の開発に成功するなど、革新的な製品展開で大躍進を遂げたという。
平塚駅周辺はちょうど七夕まつりであった。

話しには聞いていましたが、なかなか凄い飾り付け。
こんなキャラが。





お化け屋敷

夏にはやや早いですが、中から叫び声が聞こえてきました。
凄い賑わいでした。この賑わいの中にも、平塚町役場跡がありました。
脇本陣跡

脇本陣跡の近くにあった和菓子屋・安栄堂

大正5年の老舗。平塚最中を中心に、品揃えを絞っているものの、最中は美味でした。
高札場の跡

今は駅から西側で中心部とは言えない所でありますが、脇本陣跡などかつてはこの辺りが中心部だったか。
宝善院にて
日本最初の鉄道レール


この寺の檀家さんで鉄道好きの人が収集したものを寄進したそうである。
鎌倉時代の建久三年、鎌倉八幡宮寺に下向した京都・東寺の学問僧によって開山。
小田原北条氏の北条氏直は城内の守り本尊の虚空蔵菩薩を、落城寸前の城内から家来によって縁の宝善院に収めた。その名残か寺紋は「三つ鱗」である。

寺の外側の壁に、近寄ると経が流れるという。

テレビでも取り上げられたとか。
平塚宿京見付

宿場の西側の入り口。
京見付を過ぎると花水橋にて散歩かふぇの方が待っていたので休憩。
橋を渡れば大磯町に入る。
善福寺

親鸞聖人が度々相模国を訪れ、人々に念仏を勧めていた際、その教えを受けた平塚入道によって開基された寺。
平塚入道は曽我十郎祐成の子祐若 ( すけわか ) である。父の曽我十郎が仇討ちを遂げた後に生れた男子で、
成長して源実朝より平塚の荘を賜り、河津三郎信之と名乗った。
しかし、父・祖父いずれも悲運の最期を遂げた無常を感じ出家した。この時期、親鸞聖人もたびたび国府津を訪れており、平塚入道は聖人のもとを訪ね弟子となり「了源」という法名を賜り、母・虎御前の生地の近くであるこの地に草庵を結んだ。これが善福寺の創始である。
親鸞聖人の像

善福寺の境内に在る横穴群

善福寺の向かいにあった趣ある家屋


大磯のランドマーク?高麗山の麓にある高来神社へ。

神社には良く見られる力石

本殿へ参拝

高麗神社とも呼ばれる。社名は一説に朝鮮半島にあった高句麗からの渡来人に由来するといわれる。
中世の戦乱等により書物が焼失したため起源は明らかでないが、神武天皇の時代の創建とする記録があるという。
江戸時代まで高麗寺という寺が山中にあり、現在の高来神社も高麗神社として寺内にあった。高麗寺は高句麗から渡来した高麗若光を祀った古い寺院と言われるが、室町時代には数度の戦火に見舞われ、廃寺寸前にまで追い込まれる。しかし江戸時代に徳川家が権現信仰のあるこの寺を上野寛永寺の末寺とし東照宮を置いたことから隆盛を取り戻した。しかし明治時代に入るとこのことが仇となり、徳川色を消し去りたい明治政府によってこの寺は廃寺とされ、廃仏毀釈で山内の堂塔は悉く破壊され高麗神社だけが残った。高麗神社は明治時代に高来神社(たかくじんじゃ)と改名し現在に至っている。

参拝した後、神社の人が居たので朱印を受ける。すると、遠くの神社に行っているからか、色々と聞かれる。

高来神社を出て、しばらくすると大磯宿の名残が出てくる。
虚空蔵堂

高来神社がかつて高麗寺だった際、東照宮も配祀されていたため大名行列はここで下馬したという。
水車がある。

調べたら蕎麦屋の様である。
化粧井戸の跡

『曽我物語』の主人公、兄の曽我十郎の恋人である虎女は17歳で大磯の菊鶴という長者にもらいうけられ遊女になった。その虎女が化粧をする際に使用した井戸の跡であるという。
虎女は十郎が仇討ちの本望を遂げ命を落とすまでの2年間及び63歳で生涯を閉じるまでの晩年を大磯の地で暮らした。
鎌倉時代頃の大磯の中心地はこの化粧井戸の辺りであった。
大磯八景の碑

明治40年、当時の大磯町長が大磯町内の名所八か所を選んで絵葉書にした。
その内の「化粧坂の夜雨」の碑
無人販売の枝豆を良く見た。

大磯駅近くのエリザベスサンダーホーム・沢田美喜記念館

沢田美喜は岩崎弥太郎の孫娘として生まれ、外交官の沢田廉三と結婚。敗戦後、エリザベス・サンダースホームを創設し、2000人近くの混血孤児を育て上げた。
記念館はもう閉まっていたため入れなかったが、沢田美喜が収集した隠れキリシタンの遺物があるというので、見てみたいものだ。
大磯駅の向こうに見える洋館。気になる。

大磯駅にてゴール。

解散前に駅近くの喫茶店で休憩。お疲れ様でした。
お世話になっている「散歩かふぇ ちゃらぽこ」さんの企画「ホントに歩く東海道ウォーク 茅ヶ崎~大磯」に参加しました。
自分は街歩きをするに当たって街道筋は目安にしますが、街道を歩く事を目的としている訳では無いのもあって、東海道歩きは「品川~川崎・神奈川~藤沢・小田原~府中」など小間切れになっていました。
そこで、今回の企画は歩いていない茅ヶ崎~大磯を歩く企画という事で、参加です。

生憎の雨。そこそこ風も有る中、スタートです。

駅界隈は多少、歩いた事あります。
駅前から国道一号線に出て、ここから東海道を西へ進む。
観光案内所の前に居たキャラクター。

「えぼし麻呂」というらしい。茅ヶ崎に住む貴族だそうで、茅ヶ崎海岸沖の烏帽子岩からであろう。
樹齢200年超のクロマツ。

江戸時代の旅人もこの松を見たのであろう。
平成21年に枯死してしまったとか。
色々と話題になってる湘南クッキーの自販機

途中にあった竹細工の店

第六天神社

7月海の日に行われる浜降祭は、 神奈川県の民俗資料として無形文化財に指定され、茅ヶ崎海岸に近郷より三十数基神輿が集まる祭典との事。
三猿や道祖神の石碑

鉄工所のなかなかセンスある花壇が。

なかなか聞かないキャッチですね。

ナゾな落書き・・・ヘルメット?

南湖の左富士

左富士は富士市の吉原宿に向かう途中の所は知っていましたがココにも。
ココは富士山の真東に当たり、やや北西に向かう道となる事で「左」に富士がある。
南湖の左富士の側に鶴嶺八幡宮の鳥居。

東海道からはやや外れるが、八幡宮に向かう。
鶴嶺八幡宮へ向かう。

相模国茅ヶ崎の総社として往古より八幡信仰の本地として名高い。また鶴嶺八幡宮によると、源氏が関東へ進出する際、創建した最初の氏社という。





普段は水が満たされている神池ですが、この日は全く無かったです。


見事な参道

この並木は江戸時代に朝恵上人という八幡宮別当の僧侶が、当地の地頭と共に整備したという。
女護ヶ石

女性の守護神として、この石を撫でた後、体の良くない部分を撫でると良くなるという。

神社には珍しい鐘が。

習合時代の名残か。
御神木としてのイチョウ


かわらけ投げ

この石に当てる

崖などの高い所や海などではかわらけ投げやった事ありますが、こんな近い距離は初めて見ました
拝殿

針塚

がん封じ石

ここも女護ヶ石の様に、この石を撫でた後、体の良くない部分を撫でると良くなるという。
こういった石も神社としては珍しい。
末社の淡島神社

女護ヶ石はこの淡島社の関係でしょうか。
鶴嶺八幡宮から再び東海道へ。
神明社

この神社の境内にある晴明井戸の碑

安倍晴明が東国に赴いた際、喉を潤した井戸があったという。
東海道名物・でかまん菓子舗さんへ

一番大きいのは30センチ弱

大きいから味も大味・・・と言う事は無く、丁寧なこしあん。美味しく頂きました。

他の種類のお菓子も購入しました。
国指定史跡・相模川橋脚跡

鎌倉時代の御家人・稲毛重成が架橋した。その際に源頼朝が渡り初めの時に落馬し、死亡する傷を作ってしまった曰くつきの場所である。
時は大正12年の関東大震災。地震により水田から鎌倉時代の橋脚が姿を現し、調査の結果、史跡に指定された。
史跡としての重要性に加え、関東大震災の地震状況を示す天然記念物としても重要な史跡である。
そして相模川を渡ると平塚市に。

この辺りから風雨が強くなり、全身ずぶぬれに。ツラい。
橋を越えた先に在る陸軍架橋記念碑

関東大震災によって橋が落橋し、交通が寸断された。9月17日に陸軍の工兵部隊により架橋工事が行われた。10月3日に完成し、その事績を讃えた碑である。
丁髷塚

1838年、寒川神社の神輿が春に大磯で行われる国府祭に渡御した帰りに、一ノ宮の寒川神社の氏子と四ノ宮の前鳥神社の氏子とが相模川の渡し場で争いを起こし、寒川神社の御輿が川に落ちて行方不明となった。
争いは裁判となり、代官・江川英龍は前鳥神社の氏子16名に打首断罪の判決を下したが、処刑の日に代官はその丁髷だけを斬り落とし、打首に代えたという。これが丁髷塚である。
一里塚跡

日本橋から15番目の一里塚。
たまたま通り掛かった所にあった乳業メーカー・守山乳業の工場

門のすぐ内側に、創業者らしい銅像が有ったので見てみる。


調べたところ、創業は1918年1月と90年以上の歴史を持つ老舗である。
大正9年12月には日本で初めてコーヒー牛乳を製造した会社でもある。

続けて国産初の無糖練乳の開発に成功するなど、革新的な製品展開で大躍進を遂げたという。
平塚駅周辺はちょうど七夕まつりであった。

話しには聞いていましたが、なかなか凄い飾り付け。
こんなキャラが。





お化け屋敷

夏にはやや早いですが、中から叫び声が聞こえてきました。
凄い賑わいでした。この賑わいの中にも、平塚町役場跡がありました。
脇本陣跡

脇本陣跡の近くにあった和菓子屋・安栄堂

大正5年の老舗。平塚最中を中心に、品揃えを絞っているものの、最中は美味でした。
高札場の跡

今は駅から西側で中心部とは言えない所でありますが、脇本陣跡などかつてはこの辺りが中心部だったか。
宝善院にて
日本最初の鉄道レール


この寺の檀家さんで鉄道好きの人が収集したものを寄進したそうである。
鎌倉時代の建久三年、鎌倉八幡宮寺に下向した京都・東寺の学問僧によって開山。
小田原北条氏の北条氏直は城内の守り本尊の虚空蔵菩薩を、落城寸前の城内から家来によって縁の宝善院に収めた。その名残か寺紋は「三つ鱗」である。

寺の外側の壁に、近寄ると経が流れるという。

テレビでも取り上げられたとか。
平塚宿京見付

宿場の西側の入り口。
京見付を過ぎると花水橋にて散歩かふぇの方が待っていたので休憩。
橋を渡れば大磯町に入る。
善福寺

親鸞聖人が度々相模国を訪れ、人々に念仏を勧めていた際、その教えを受けた平塚入道によって開基された寺。
平塚入道は曽我十郎祐成の子祐若 ( すけわか ) である。父の曽我十郎が仇討ちを遂げた後に生れた男子で、
成長して源実朝より平塚の荘を賜り、河津三郎信之と名乗った。
しかし、父・祖父いずれも悲運の最期を遂げた無常を感じ出家した。この時期、親鸞聖人もたびたび国府津を訪れており、平塚入道は聖人のもとを訪ね弟子となり「了源」という法名を賜り、母・虎御前の生地の近くであるこの地に草庵を結んだ。これが善福寺の創始である。
親鸞聖人の像

善福寺の境内に在る横穴群

善福寺の向かいにあった趣ある家屋


大磯のランドマーク?高麗山の麓にある高来神社へ。

神社には良く見られる力石

本殿へ参拝

高麗神社とも呼ばれる。社名は一説に朝鮮半島にあった高句麗からの渡来人に由来するといわれる。
中世の戦乱等により書物が焼失したため起源は明らかでないが、神武天皇の時代の創建とする記録があるという。
江戸時代まで高麗寺という寺が山中にあり、現在の高来神社も高麗神社として寺内にあった。高麗寺は高句麗から渡来した高麗若光を祀った古い寺院と言われるが、室町時代には数度の戦火に見舞われ、廃寺寸前にまで追い込まれる。しかし江戸時代に徳川家が権現信仰のあるこの寺を上野寛永寺の末寺とし東照宮を置いたことから隆盛を取り戻した。しかし明治時代に入るとこのことが仇となり、徳川色を消し去りたい明治政府によってこの寺は廃寺とされ、廃仏毀釈で山内の堂塔は悉く破壊され高麗神社だけが残った。高麗神社は明治時代に高来神社(たかくじんじゃ)と改名し現在に至っている。

参拝した後、神社の人が居たので朱印を受ける。すると、遠くの神社に行っているからか、色々と聞かれる。

高来神社を出て、しばらくすると大磯宿の名残が出てくる。
虚空蔵堂

高来神社がかつて高麗寺だった際、東照宮も配祀されていたため大名行列はここで下馬したという。
水車がある。

調べたら蕎麦屋の様である。
化粧井戸の跡

『曽我物語』の主人公、兄の曽我十郎の恋人である虎女は17歳で大磯の菊鶴という長者にもらいうけられ遊女になった。その虎女が化粧をする際に使用した井戸の跡であるという。
虎女は十郎が仇討ちの本望を遂げ命を落とすまでの2年間及び63歳で生涯を閉じるまでの晩年を大磯の地で暮らした。
鎌倉時代頃の大磯の中心地はこの化粧井戸の辺りであった。
大磯八景の碑

明治40年、当時の大磯町長が大磯町内の名所八か所を選んで絵葉書にした。
その内の「化粧坂の夜雨」の碑
無人販売の枝豆を良く見た。

大磯駅近くのエリザベスサンダーホーム・沢田美喜記念館

沢田美喜は岩崎弥太郎の孫娘として生まれ、外交官の沢田廉三と結婚。敗戦後、エリザベス・サンダースホームを創設し、2000人近くの混血孤児を育て上げた。
記念館はもう閉まっていたため入れなかったが、沢田美喜が収集した隠れキリシタンの遺物があるというので、見てみたいものだ。
大磯駅の向こうに見える洋館。気になる。

大磯駅にてゴール。

解散前に駅近くの喫茶店で休憩。お疲れ様でした。
2015年09月24日
10月3日講演「式年遷宮 永遠なる常若の宮」 三島市 カフェうーるーにて
10月3日9時半から三島市のカフェうーるーにて行います。
内容は「式年遷宮 永遠なる常若の宮」です。

(遷宮が行われたばかりの内宮)
日本最大の聖地とされる伊勢神宮。
この宮は宝物に至るまで20年の間隔で全く新しく造り替えられる。
この習慣はなぜ生まれたのか、伊勢神宮が聖地とされた背景から、現在に至るまでの遷宮についてお話しします。
「古代史・伊勢神宮・建築史・式年遷宮・斎宮・持続可能社会・飛鳥時代に関心がある方におすすめです。」
会費:500円+ワンドリンクオーダー
時間:9時から11時半予定
開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)
参加の申し込み不要。
問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「式年遷宮 永遠なる常若の宮」です。

(遷宮が行われたばかりの内宮)
日本最大の聖地とされる伊勢神宮。
この宮は宝物に至るまで20年の間隔で全く新しく造り替えられる。
この習慣はなぜ生まれたのか、伊勢神宮が聖地とされた背景から、現在に至るまでの遷宮についてお話しします。
「古代史・伊勢神宮・建築史・式年遷宮・斎宮・持続可能社会・飛鳥時代に関心がある方におすすめです。」
会費:500円+ワンドリンクオーダー
時間:9時から11時半予定
開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)
参加の申し込み不要。
問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2015年09月23日
伊豆経済大学に出展しています!
22日・23日、ホテル昭明館での開催の伊豆経済大学、初日が終わりました。
どうしても導線が他の展示と違うからか、通り過ぎてしまう方も居るのですが・・・私は400号室に居ます。
ちょっと殺風景だったのを改善しなくては・・・

今日はもっと展示を拡充します。
壁面に波のデザインを描いてくれた学生の皆さんにも感謝です。
作業中に展示の話しなどしましたが、「今まで歴史に興味無かったけど、こんな授業だったらもっと関心持ったのに」と、話しをした二人が4人連れて話が聴きたいと言ってくれたのは嬉しかったです。
作業しただけだったら、伊豆に関心持つ事は殆ど無かったと思いますが、こうして印象に残せたなら展示の甲斐もあります。
講座始めてから感じている一貫した手応えとして、女性の方が歴史の面白さ、と言うのを感じてくれる方が多い気がします。
あと、三島の街は高い所からの風景を見る所が余り無いので、私が4階にいた事もあり、が来てない時は上からの眺めを楽しんでおりました。
伊豆経済大学で屋上からの風景を見つつ食事も如何でしょうか。
子供向けに用意した発掘体験キット、途中で追加するほどの盛況でした!

今日も10時から17時まで、展示しています!お待ちしています。
どうしても導線が他の展示と違うからか、通り過ぎてしまう方も居るのですが・・・私は400号室に居ます。
ちょっと殺風景だったのを改善しなくては・・・
今日はもっと展示を拡充します。
壁面に波のデザインを描いてくれた学生の皆さんにも感謝です。
作業中に展示の話しなどしましたが、「今まで歴史に興味無かったけど、こんな授業だったらもっと関心持ったのに」と、話しをした二人が4人連れて話が聴きたいと言ってくれたのは嬉しかったです。
作業しただけだったら、伊豆に関心持つ事は殆ど無かったと思いますが、こうして印象に残せたなら展示の甲斐もあります。
講座始めてから感じている一貫した手応えとして、女性の方が歴史の面白さ、と言うのを感じてくれる方が多い気がします。
あと、三島の街は高い所からの風景を見る所が余り無いので、私が4階にいた事もあり、が来てない時は上からの眺めを楽しんでおりました。
伊豆経済大学で屋上からの風景を見つつ食事も如何でしょうか。
子供向けに用意した発掘体験キット、途中で追加するほどの盛況でした!

今日も10時から17時まで、展示しています!お待ちしています。
2015年09月16日
9月30日講演 「賀川豊彦 俗を行き交う聖人」 沼津市 高嶋酒造にて
9月30日18時半より講演致します。
内容は「賀川豊彦 俗を行き交う聖人」です。

(若き日の賀川豊彦)
キリスト教の信念をもって、貧しい人々の中に入り救済活動を行った賀川豊彦。
目の前の人を助けるだけでなく、社会の問題を変えるべく私費を投じて多くの人を巻き込み国の枠をも超えていった。
大正から昭和に掛けて、あらゆる社会運動を立ち上げたと言われる賀川豊彦の生涯についてお話しします。
「社会運動・協同組合・労働運動・救貧活動」に関心がある方にオススメ。
参加費:700円。
時間:18時30分から
開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて
※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)
※自由参加ですが、問い合わせ等は高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「賀川豊彦 俗を行き交う聖人」です。
(若き日の賀川豊彦)
キリスト教の信念をもって、貧しい人々の中に入り救済活動を行った賀川豊彦。
目の前の人を助けるだけでなく、社会の問題を変えるべく私費を投じて多くの人を巻き込み国の枠をも超えていった。
大正から昭和に掛けて、あらゆる社会運動を立ち上げたと言われる賀川豊彦の生涯についてお話しします。
「社会運動・協同組合・労働運動・救貧活動」に関心がある方にオススメ。
参加費:700円。
時間:18時30分から
開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて
※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)
※自由参加ですが、問い合わせ等は高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2015年09月15日
高山本線を行く
※この記事は2013年の記事を再編集した物です。
6:44起床 7:00 出 7:05 朝食購入
7:38呉羽発 通勤・通学で込み入ってる。
7:44富山駅 降りて周辺を少し散策

富山駅も新幹線開通に向けて色々と工事中

富山所縁の安田善次郎の像

富山の薬売りの像


8:14高山本線発 高山本線は初めてである。

カーテンが風情ある
曇っているが、北アルプスや立山が見える。

楡原周辺は雨が降った跡がある。
東八尾駅を過ぎると、線路は神通川に沿って行く。

神一ダム



雪かきをするための機材が駅に置かれるようになってきた。

9:05猪谷駅乗り換え JR西日本と東海の境である。

かつては神岡線も乗り入れていたが廃線。その名残であろう。

9:11発
この辺りから山深い渓谷沿いの路線に。

時々ダムがあり、山は雪がまだ深く残っている。
10:18高山駅 かなりの人が下車。やはり観光地である。

10:24 発
岐阜県白川町の上麻生堰堤


1926年、松永安左エ門率いる東邦電力が施工・完成させた。
飛水峡(岐阜県加茂郡七宗町)

約12kmの峡谷。甌穴が数多く見られ「飛水峡の甌穴群」として国の天然記念物に指定されている。
13:12 美濃太田駅着

美濃太田駅はJR東海の高山本線と太多線、長良川鉄道の越美南線の3路線が乗り入れ、接続駅となっている交通の要衝である。
次発までの時間で美濃太田駅周辺を散策。

駅前のモニュメント

駅前通りの道沿いに黄道12星座の銅像が並んでいる。










スーパーでカメヤのわさびドレッシング発見。

どんな漬物なのか?

そして駅に戻った時にあった坪内逍遥の像。

この地の出身だという事だ。個人的には熱海のイメージが強かった。
13:56発
坂祝駅過ぎた所に、自分の講座でも取り上げた川上貞奴が建立した貞照寺が。
14:32岐阜着 14:38 東海道線に乗り換え。
ここでカメラを高山本線の列車に忘れた事を気付く。尾張一宮で取って返して岐阜駅で忘れ物手続き。自分が乗っていた列車は飛騨古川行きとなったので、今からでは行ったら今日中に帰れないので、ここはJRさんに託すことにする。
15:23 岐阜発 東海道線新快速~16:39 豊橋着 16:42発~17:15 浜松 17:20発 新所原でもwimax使える!エリア広がってるな。菊川までつかえた。
17:02新蒲原にて下車。よし川さんで食事。
21:19新蒲原~21:50三島 下車
帰宅
6:44起床 7:00 出 7:05 朝食購入
7:38呉羽発 通勤・通学で込み入ってる。
7:44富山駅 降りて周辺を少し散策

富山駅も新幹線開通に向けて色々と工事中

富山所縁の安田善次郎の像

富山の薬売りの像


8:14高山本線発 高山本線は初めてである。

カーテンが風情ある
曇っているが、北アルプスや立山が見える。

楡原周辺は雨が降った跡がある。
東八尾駅を過ぎると、線路は神通川に沿って行く。

神一ダム



雪かきをするための機材が駅に置かれるようになってきた。

9:05猪谷駅乗り換え JR西日本と東海の境である。

かつては神岡線も乗り入れていたが廃線。その名残であろう。

9:11発
この辺りから山深い渓谷沿いの路線に。

時々ダムがあり、山は雪がまだ深く残っている。
10:18高山駅 かなりの人が下車。やはり観光地である。

10:24 発
岐阜県白川町の上麻生堰堤


1926年、松永安左エ門率いる東邦電力が施工・完成させた。
飛水峡(岐阜県加茂郡七宗町)

約12kmの峡谷。甌穴が数多く見られ「飛水峡の甌穴群」として国の天然記念物に指定されている。
13:12 美濃太田駅着

美濃太田駅はJR東海の高山本線と太多線、長良川鉄道の越美南線の3路線が乗り入れ、接続駅となっている交通の要衝である。
次発までの時間で美濃太田駅周辺を散策。

駅前のモニュメント

駅前通りの道沿いに黄道12星座の銅像が並んでいる。










スーパーでカメヤのわさびドレッシング発見。

どんな漬物なのか?

そして駅に戻った時にあった坪内逍遥の像。

この地の出身だという事だ。個人的には熱海のイメージが強かった。
13:56発
坂祝駅過ぎた所に、自分の講座でも取り上げた川上貞奴が建立した貞照寺が。
14:32岐阜着 14:38 東海道線に乗り換え。
ここでカメラを高山本線の列車に忘れた事を気付く。尾張一宮で取って返して岐阜駅で忘れ物手続き。自分が乗っていた列車は飛騨古川行きとなったので、今からでは行ったら今日中に帰れないので、ここはJRさんに託すことにする。
15:23 岐阜発 東海道線新快速~16:39 豊橋着 16:42発~17:15 浜松 17:20発 新所原でもwimax使える!エリア広がってるな。菊川までつかえた。
17:02新蒲原にて下車。よし川さんで食事。
21:19新蒲原~21:50三島 下車
帰宅
2015年09月14日
9月13日 ちゃらぽこ講演 「孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」 参考文献
9月13日、散歩かふぇ ちゃらぽこにて「孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」についてお話させて頂きました。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「小笠原学ことはじめ/ダニエル・ロング 」
「幕末の小笠原: 欧米の捕鯨船で栄えた緑の島/田中弘之 」
「近代日本と小笠原諸島: 移動民の島々と帝国/石原俊」
「硫黄島と小笠原をめぐる日米関係/ロバート・D・エルドリッヂ」
ご参考にしてください。
※次回の散歩かふぇ ちゃらぽこでの講座は10月11日15時から、「果ての島の物語 玉置半衛右門と欲望の渡り鳥たち」と題し、明治期に盛んになった無人島開拓の歴史を、玉置商会という会社を通じてお話しします。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「小笠原学ことはじめ/ダニエル・ロング 」
「幕末の小笠原: 欧米の捕鯨船で栄えた緑の島/田中弘之 」
「近代日本と小笠原諸島: 移動民の島々と帝国/石原俊」
「硫黄島と小笠原をめぐる日米関係/ロバート・D・エルドリッヂ」
ご参考にしてください。
※次回の散歩かふぇ ちゃらぽこでの講座は10月11日15時から、「果ての島の物語 玉置半衛右門と欲望の渡り鳥たち」と題し、明治期に盛んになった無人島開拓の歴史を、玉置商会という会社を通じてお話しします。
2015年09月13日
本日講演 「孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」 散歩かふぇ ちゃらぽこにて
本日15時より散歩かふぇ ちゃらぽこにて講演致します。
内容は「孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」です。

(小笠原開拓の中心に居たセーボリー一家)
日本の領土でありながら、日本人では無い人々によって拓かれた島・小笠原。
無人島(むにんしま)と呼ばれ、漂流民が漂着する日本の果てであった島が、太平洋の最後のフロンティアとして欧米各国の注目を集めた。その状態で日本は領土として主張するために如何に動いたのか。
20を超える国と地域から集まった欧米系島民たちによって育まれた小笠原諸島の歴史と文化についてお話します。
「明治時代・太平洋航路・近代史・領土問題・クレオール文化」に関心がある方にオススメ。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」です。

(小笠原開拓の中心に居たセーボリー一家)
日本の領土でありながら、日本人では無い人々によって拓かれた島・小笠原。
無人島(むにんしま)と呼ばれ、漂流民が漂着する日本の果てであった島が、太平洋の最後のフロンティアとして欧米各国の注目を集めた。その状態で日本は領土として主張するために如何に動いたのか。
20を超える国と地域から集まった欧米系島民たちによって育まれた小笠原諸島の歴史と文化についてお話します。
「明治時代・太平洋航路・近代史・領土問題・クレオール文化」に関心がある方にオススメ。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2015年09月11日
城下町と職人の街 高岡市散策
※この記事は2013年の記事を再編集した物です。
来年度に北陸新幹線が出来るという事で、在来線が18きっぷが使えなくなる前に北陸に行くことにする。
7:10三島~9:20磐田
所要を済ませる。
13:03磐田~13:21浜松~13:55豊橋14:03~15:37大垣~

伊吹山は所々雪が残っている。
16:10米原 北陸本線に乗り換えも、人身事故で4分ほど遅れ。 16:30発
16:41長浜 米原から3駅で終点。駅から見た様子も歩いてみたい雰囲気がある。
17:06近江塩津 また6駅ほどで終点。17:10に次発の筈だが来ない・・・。それに非常に寒い。真冬並みの寒さ。待ってる間に特急が三本通り抜ける。

17:30に到着。人身事故の影響で遅れているようだ。

17:52敦賀 また二駅で終点・・・。
20:32金沢 次発まで30分あるので買い物。

金沢駅のキオスクで福井名物ボルガライスなる弁当発見。オムライスにカツが乗ってる。

金沢カレーもそうだが、北陸はカツをよく使うな。 21:03発。
21:52呉羽着

歩いて今日の宿泊ネットカフェへ。
22:15ネットカフェ着 本日終了
6:30 起床~7:15 出発~
7:30 姉倉比売神社

まっすぐ駅に向かっていたが神社の看板があり、行ってみるとなかなか古い神社であった。地名由来もあるだろう。
神社から立山方面を望む

7:56 呉羽駅発~

昨日の夜は気付かなかったが、北陸新幹線の高架が出来つつある。
8:15高岡駅着



高岡の街づくりを行った加賀二代目藩主・前田利長のゆるキャラ「としながくん」がお出迎え。

萌えキャラ?



高岡は鋳物の街、という事での展示


高岡駅は新幹線の開通に備えて改修中であるが、駅前の景観は褒められたものではない。

路面電車の万葉線


末広町という地名ですので…。

高岡市の再開発ビル前にあるドラえもんキャラクターの像

ちなみに、このビルの中にある市立図書館には藤子F不二夫氏の作品を網羅しているという。
路地が非常に多い。



8:30 関野神社

45発
関野神社から商店街を歩いて高岡城跡公園に向かう。
商店街はアーケードで一見歩道かと思いきや、車道で車が急に走ってきて来るので要注意である。
歩いていると、銅像が非常に多い。これも鋳物の街であるからか。










最大の鋳物作品とも言える高岡大仏が街中にあって驚き。

歩いていて予期せず現れた感じである。
9:05 高岡城址の公園に入る。すると、市立博物館があり『無料』とあったので入る。

展示内容は、高岡市の街づくりにおける前田氏に関して、高岡の鋳物に関して、その他の伝統工芸に関してであった。見応えもあった。そこそこ人も来ている。
あと、休憩スペースに藤子F不二夫先生の漫画が色々と揃えてあり、インタビュー本など色々と読んでみる。
博物館の建物も昔行われた博覧会の美術館であった所である。


12:00 出
公園の中には動物園がある。

ここも無料で見ることが出来る。






職員の人の手書きイラストが面白いので一挙公開。




















動物園から東に歩いていると見掛けた井戸

この高岡城は築城当時に前田家に身を寄せていた高山右近が縄張りを行ったという。これは非常に新鮮な発見だった。
ココから本丸の方へ。

この広い空間の周辺に再び銅像のラッシュである。
木下繁『裸婦』

北村西望『夢』

富永直樹「私の家族」

斎藤素巌「行路」



澤田政廣「レダ」

熱海の澤田政廣作品をココで見られるとは。
前田藩二代目にして高岡の街づくりを行った前田利長像

古賀忠雄「鶏舎の朝」


佐藤助雄『地と風』

12:30 射水神社

城内と言うことで、藩祖を祀った神社かと思っていたが、非常に古い神社であった。

13:00出

城跡公園を後にし、金屋町に向かって歩く。
その途中の山町筋の土蔵の町並みもなかなか。
山町は高岡の町が開かれてから、越中の物資の集散地として栄えた。
明治33年の大火以後に建築されたたため、当時の耐火要件を備えた建物が多い。






筏井家住宅 主屋

明治36年の建築。糸などを扱う卸商であった。富山県指定有形文化財に指定されている。




菅野家住宅


廻船業を行い、明治期に銀行や電燈業も行う高岡の名士であった。








もう少し景観制限をして、車の通りを制限してくれると歩き易いか。
気になる店もある。

そして、化学者・高峰譲吉の旧家跡

高岡鋳物の町筋。金屋町に。

金屋町は若干、市の中心から離れているが、鋳物という高温の金属を扱う業種ゆえ、火事を避けるため川の向こうに設けられた。

金屋町も雰囲気は良いが車が時々勢い良く走って来るので危ない。

建物も銅板を使っているのが多い。

自宅前に作品を展示している家も多い。

金屋町は表札を見ても、「鍛冶」「鍋谷」など、金属加工にちなんだ姓をよく見た。
登録有形文化財 旧南部鋳造所のキュポラと煙突





そして休憩できるカフェなどが欲しい。
肉屋があったので、コロッケなどを購入。高岡もコロッケで売り出しているようだ。
高岡駅の南側に出る。

八丁道という前田家の菩提寺・瑞龍寺から墓所までの道へ。


前田利長墓所

旧藩時代ならともかく、現代にも菩提寺と墓所を結ぶ道が真っ直ぐ繋がっているのが凄い。
駅近くのスーパーへ。意外に静岡の物産が売られている。
駅前に戻って、駅で土産購入。そして駅前の路地を歩き尽くす。






孝子六兵衛の碑という親孝行で藩からも褒賞を貰った人の碑


図書館へ。高岡市出身の藤子不二夫氏の作品がすべて揃えてある。他にも公立図書館では見ないような漫画も数多い。
図書館は20時終了。
下にあったラーメン屋で富山ブラックを食べる。

味は…私には濃すぎる・・・。健康診断前には食べてはいけない物ですね。
21:10 高岡発 またもや人身事故で遅れている。
21:40 呉羽着
22:10 ネットカフェ着 本日終了
来年度に北陸新幹線が出来るという事で、在来線が18きっぷが使えなくなる前に北陸に行くことにする。
7:10三島~9:20磐田
所要を済ませる。
13:03磐田~13:21浜松~13:55豊橋14:03~15:37大垣~

伊吹山は所々雪が残っている。
16:10米原 北陸本線に乗り換えも、人身事故で4分ほど遅れ。 16:30発
16:41長浜 米原から3駅で終点。駅から見た様子も歩いてみたい雰囲気がある。
17:06近江塩津 また6駅ほどで終点。17:10に次発の筈だが来ない・・・。それに非常に寒い。真冬並みの寒さ。待ってる間に特急が三本通り抜ける。

17:30に到着。人身事故の影響で遅れているようだ。

17:52敦賀 また二駅で終点・・・。
20:32金沢 次発まで30分あるので買い物。

金沢駅のキオスクで福井名物ボルガライスなる弁当発見。オムライスにカツが乗ってる。

金沢カレーもそうだが、北陸はカツをよく使うな。 21:03発。
21:52呉羽着

歩いて今日の宿泊ネットカフェへ。
22:15ネットカフェ着 本日終了
6:30 起床~7:15 出発~
7:30 姉倉比売神社

まっすぐ駅に向かっていたが神社の看板があり、行ってみるとなかなか古い神社であった。地名由来もあるだろう。
神社から立山方面を望む

7:56 呉羽駅発~

昨日の夜は気付かなかったが、北陸新幹線の高架が出来つつある。
8:15高岡駅着



高岡の街づくりを行った加賀二代目藩主・前田利長のゆるキャラ「としながくん」がお出迎え。

萌えキャラ?



高岡は鋳物の街、という事での展示


高岡駅は新幹線の開通に備えて改修中であるが、駅前の景観は褒められたものではない。

路面電車の万葉線


末広町という地名ですので…。

高岡市の再開発ビル前にあるドラえもんキャラクターの像

ちなみに、このビルの中にある市立図書館には藤子F不二夫氏の作品を網羅しているという。
路地が非常に多い。



8:30 関野神社

45発
関野神社から商店街を歩いて高岡城跡公園に向かう。
商店街はアーケードで一見歩道かと思いきや、車道で車が急に走ってきて来るので要注意である。
歩いていると、銅像が非常に多い。これも鋳物の街であるからか。










最大の鋳物作品とも言える高岡大仏が街中にあって驚き。

歩いていて予期せず現れた感じである。
9:05 高岡城址の公園に入る。すると、市立博物館があり『無料』とあったので入る。

展示内容は、高岡市の街づくりにおける前田氏に関して、高岡の鋳物に関して、その他の伝統工芸に関してであった。見応えもあった。そこそこ人も来ている。
あと、休憩スペースに藤子F不二夫先生の漫画が色々と揃えてあり、インタビュー本など色々と読んでみる。
博物館の建物も昔行われた博覧会の美術館であった所である。


12:00 出
公園の中には動物園がある。

ここも無料で見ることが出来る。






職員の人の手書きイラストが面白いので一挙公開。




















動物園から東に歩いていると見掛けた井戸

この高岡城は築城当時に前田家に身を寄せていた高山右近が縄張りを行ったという。これは非常に新鮮な発見だった。
ココから本丸の方へ。

この広い空間の周辺に再び銅像のラッシュである。
木下繁『裸婦』

北村西望『夢』

富永直樹「私の家族」

斎藤素巌「行路」



澤田政廣「レダ」

熱海の澤田政廣作品をココで見られるとは。
前田藩二代目にして高岡の街づくりを行った前田利長像

古賀忠雄「鶏舎の朝」


佐藤助雄『地と風』

12:30 射水神社

城内と言うことで、藩祖を祀った神社かと思っていたが、非常に古い神社であった。

13:00出

城跡公園を後にし、金屋町に向かって歩く。
その途中の山町筋の土蔵の町並みもなかなか。
山町は高岡の町が開かれてから、越中の物資の集散地として栄えた。
明治33年の大火以後に建築されたたため、当時の耐火要件を備えた建物が多い。






筏井家住宅 主屋

明治36年の建築。糸などを扱う卸商であった。富山県指定有形文化財に指定されている。




菅野家住宅


廻船業を行い、明治期に銀行や電燈業も行う高岡の名士であった。








もう少し景観制限をして、車の通りを制限してくれると歩き易いか。
気になる店もある。

そして、化学者・高峰譲吉の旧家跡

高岡鋳物の町筋。金屋町に。

金屋町は若干、市の中心から離れているが、鋳物という高温の金属を扱う業種ゆえ、火事を避けるため川の向こうに設けられた。

金屋町も雰囲気は良いが車が時々勢い良く走って来るので危ない。

建物も銅板を使っているのが多い。

自宅前に作品を展示している家も多い。

金屋町は表札を見ても、「鍛冶」「鍋谷」など、金属加工にちなんだ姓をよく見た。
登録有形文化財 旧南部鋳造所のキュポラと煙突





そして休憩できるカフェなどが欲しい。
肉屋があったので、コロッケなどを購入。高岡もコロッケで売り出しているようだ。
高岡駅の南側に出る。

八丁道という前田家の菩提寺・瑞龍寺から墓所までの道へ。


前田利長墓所

旧藩時代ならともかく、現代にも菩提寺と墓所を結ぶ道が真っ直ぐ繋がっているのが凄い。
駅近くのスーパーへ。意外に静岡の物産が売られている。
駅前に戻って、駅で土産購入。そして駅前の路地を歩き尽くす。






孝子六兵衛の碑という親孝行で藩からも褒賞を貰った人の碑


図書館へ。高岡市出身の藤子不二夫氏の作品がすべて揃えてある。他にも公立図書館では見ないような漫画も数多い。
図書館は20時終了。
下にあったラーメン屋で富山ブラックを食べる。

味は…私には濃すぎる・・・。健康診断前には食べてはいけない物ですね。
21:10 高岡発 またもや人身事故で遅れている。
21:40 呉羽着
22:10 ネットカフェ着 本日終了